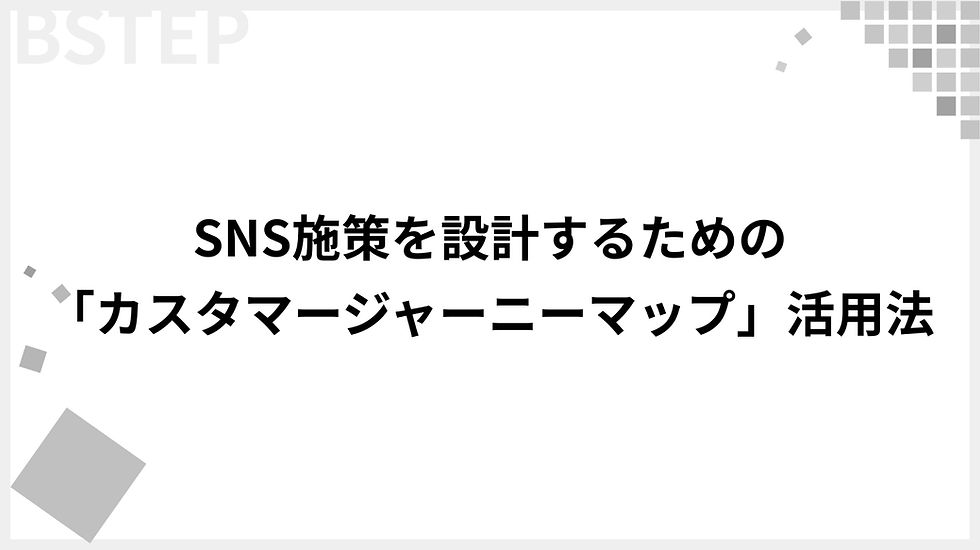【2026年最新版】クリニックの集患にYouTube運用がおすすめ!選ばれる理由と成功のポイントを徹底解説
- 2025年9月26日
- 読了時間: 16分
更新日:1月5日

 この記事の著者 | 山口巧己 地方×SNSマーケティングのスペシャリスト 大学在学中からSNSを独学し、父の車屋やインターンでのアウトドアブランドのSNS運用を行い、認知拡大・販売促進の向上、副次的に採用への貢献。この経験から紹介での依頼をいただき、大学4年生でフリーランスとして活動。 卒業後、WEBベンチャー企業で新規顧客開拓の営業へ従事する傍ら、フリーランス活動を継続。入社9ヶ月で退職し、独立。これまでの支援社数は50社を超える。 運用の"代行"ではなく、クライアントの経営戦略から逆算して結果へ繋げるためのSNSマーケティングが得意。 いい商品・サービス・会社を広めることが好きなSNSマーケオタク。 |
「患者数が思うように伸びない」
「地域での認知度が低い」
「競合クリニックとの差別化が難しい」
──こうした悩みを抱える整形外科、歯科、皮膚科、内科、美容クリニックなどにとって、YouTube運用は効果的な解決策になります。
動画で医師やスタッフの人柄を伝えることで患者に安心感を与えられ、治療内容も分かりやすく説明できるため、集患やブランディングに直結します。
本記事では、クリニックがYouTubeを活用すべき理由や具体的なメリット、成功事例や注意点、さらに成果を出すためのステップを徹底解説します。
読み進めることで、貴院に合ったYouTube活用の第一歩が見えてくるはずです。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するYouTube施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。
少しでも興味をお持ちの方は、下記のリンクから詳細をチェックしてみましょう。
なぜ今、クリニックにYouTube運用が求められているのか |

医療機関の情報発信といえば、これまではホームページや口コミサイトが中心でした。
しかし最近では、患者が病院を探す際にまずYouTubeで検索し、動画を見てから来院を検討するケースが増えています。
つまり、クリニックにとっても動画を通じた情報発信は無視できないものになってきたのです。
この背景には主に次の3つの理由があります。
患者が「まず動画で調べる」時代になった
医師やスタッフの人柄を伝えることで安心感を与えられる
他院との差別化につながる情報発信が可能になる
これらの要素が重なり、YouTubeはクリニックにとって信頼構築と集患を同時に実現できる新しいチャネルとして注目されています。
患者が「まず動画で調べる」時代になった
クリニックにYouTube運用が求められている理由のひとつは、患者が情報収集の際に動画を活用することが当たり前になったからです。
なぜなら、動画はテキストや画像に比べて圧倒的に多くの情報を短時間で伝えられるため、初めての診療や治療に不安を感じる患者にとって理解しやすいからです。例えば「クリニックの雰囲気」「治療の流れ」「医師の人柄」などは文章だけでは伝わりにくいですが、動画ならリアルに確認できます。
実際に、検索行動のトレンドとして「病院名+治療名」でYouTubeを調べるケースが増加しており、動画を見てから予約する流れが定着しつつあります。
つまり、患者が選ぶ基準において、動画は重要な役割を果たしているのです。
人柄を伝えることで安心感を与えられる
クリニックにとってYouTubeが有効なもうひとつの理由は、医師やスタッフの人柄を伝えられることです。
理由としては、患者は「誰に診てもらうのか」を重視しており、信頼感が来院の大きな決め手になるからです。文章や写真だけでは堅い印象になりがちですが、動画では医師の話し方や表情、院内の雰囲気が自然に伝わります。これによって患者は「ここなら安心して相談できそうだ」と感じやすくなります。
たとえば、初診で緊張しやすい患者でも、事前に医師やスタッフの動画を視聴していれば心理的なハードルが下がり、来院後の満足度も高まりやすくなります。
つまり、人柄を見せられる動画は、信頼関係を築く第一歩として非常に有効なのです。
他院との差別化につながる情報発信が可能
さらに、YouTubeは他院との差別化を図る有力な手段でもあります。
なぜなら、まだ多くのクリニックが動画運用に本格的に取り組んでいないため、早く始めることで地域内で目立ちやすくなるからです。医療に関する解説や患者へのアドバイスを動画で提供すれば、専門性や独自の強みを発信でき、他院との違いを示せます。
例えば、美容クリニックであれば施術の流れを公開したり、内科クリニックであれば生活習慣病予防に関する情報を配信することで、患者にとって役立つ知識を提供できます。
これにより、単なる医療機関としてではなく「信頼できる情報発信者」としての立場を築くことができるのです。
クリニックがYouTube運用で得られる具体的なメリット |

クリニックがYouTubeを運用する最大の魅力は、ただ集患につながるだけではありません。
動画というメディアを活用することで、患者との信頼関係の構築や院内ブランディングの強化、さらには採用活動にまで効果を発揮します。
ここでは、クリニックにとっての主なメリットを整理し、なぜ今YouTubeが注目されているのかを解説します。
来院前の安心感を与えられる
YouTubeは、患者にとって来院前の不安を取り除く有効なツールです。
なぜなら、動画を通じて院内の様子や医師・スタッフの雰囲気を事前に知ることができるからです。
文字や写真だけではわかりにくい部分も、動画なら自然な形で伝わり、患者は「ここなら大丈夫そうだ」と思いやすくなります。
例えば、初めて診察を受ける患者にとっては「先生はどんな人か」「院内は清潔か」といった点が大きな関心事です。
動画でそれを紹介するだけで、来院のハードルを下げ、安心感を与えることができます。つまり、
YouTubeは信頼を築くための第一歩となるのです。
治療内容をわかりやすく伝えられる
クリニックにとって大切なのは、専門的な治療や検査の内容を患者に正しく理解してもらうことです。YouTubeはその説明手段として非常に効果的です。
その理由は、動画であれば医師が直接話しながら図や映像を交えて解説でき、患者が直感的に理解しやすいからです。文章では難解に感じる医療情報も、動画にすることでわかりやすく整理できます。
例えば、歯科であれば「矯正治療の流れ」、内科であれば「生活習慣病予防のポイント」といったテーマを動画化することで、患者の理解度が高まり、不安や誤解を防ぐことができます。
結果的に、患者の納得度や治療への協力度も向上します。
既存患者との関係性を深められる
YouTubeは新規患者の獲得だけでなく、既存患者との関係性強化にも役立ちます。
理由として、通院中の患者に向けてアフターフォローや健康管理のアドバイスを動画で提供できるからです。動画で繰り返し情報に触れてもらうことで、診察時間外でも患者とつながりを保つことができます。
例えば、皮膚科であれば「自宅でできるスキンケア方法」、内科であれば「薬の正しい服用方法」を発信すれば、患者は安心して日常生活を送ることができます。
結果的に信頼関係が深まり、リピート来院や口コミにもつながります。
採用や院内ブランディングにも効果的
クリニックにとってYouTubeは、集患だけでなく採用広報やスタッフ教育の場としても活用できます。
なぜなら、動画を通じて職場の雰囲気やスタッフの働き方を伝えることで、求職者にとって働くイメージを具体的に描けるからです。写真だけの求人票では伝わらないリアルな情報を補うことができます。
例えば、院内イベントの様子やスタッフインタビューを紹介する動画は、応募者の安心感や共感を呼び、採用活動を後押しします。また、研修動画として活用すれば、スタッフ教育の効率化にもつながります。
つまり、YouTubeは院全体の価値を高めるブランディングにも直結するのです。
【事例紹介】YouTubeで情報発信するクリニックのチャンネル |

ここまで、クリニックにおけるYouTube運用のメリットを解説してきました。
とはいえ、実際にどのようなチャンネル運営をすればよいのか、イメージが湧きにくい方も多いのではないでしょうか。参考になるのは、すでに情報発信を行っているクリニックの事例です。
ここでは、美容外科から地域医療まで4つのチャンネルを取り上げ、それぞれの特徴を紹介します。
取り上げるチャンネルは次のとおりです。
高須クリニック【公式】(高須銀座院)
天正龍一のアマソラクリニック
元神チャンネル
べっぷ内科クリニック
それぞれ異なる強みや工夫があり、自院に合った発信テーマを考えるうえで大きなヒントとなるでしょう。
銀座高須クリニック公式
高須クリニックの公式チャンネルは、美容外科に関する専門情報を発信している代表的な事例です。治療の流れや施術の内容を動画で紹介することで、視聴者に安心感を与えています。
なぜなら、専門性の高い内容を医師自身が登場して解説することで、正確性と信頼性を担保しているからです。実際に、動画を視聴した人が「顔が見える説明」で不安を軽減し、来院の判断をするケースも増えています。
まとめると、専門性を動画で表現することで、患者にとって信頼できる情報源となり、集患やブランディングにつながる好例だといえます。
ドラゴン細井featアマソラクリニックch
アマソラクリニックのチャンネルは、医師が直接カメラの前で語るスタイルを中心に展開しています。美容外科や皮膚科の専門知識を、一般の方にも理解しやすい言葉に置き換えて発信している点が特徴です。
なぜなら、医療情報は難解になりがちですが、わかりやすい言葉で語ることで「親しみやすさ」と「信頼感」を両立できるからです。実際にこのチャンネルでは、視聴者が医師の考え方や人柄を知ることで「相談しやすいクリニック」として認知を広げています。
まとめると、専門性を保ちつつも親しみやすい発信を続けることで、患者が安心してアプローチできるチャンネルの成功例となっています。
元神チャンネル
クリニックのYouTube運用において、専門性を活かした発信の好例が「元神チャンネル」です。このチャンネルは男性の性的な悩みに焦点を当て、包茎や増大、早漏といったデリケートなテーマを扱っています。
なぜなら、これらの悩みは人前で相談しにくいため、匿名で学べるYouTubeという媒体が適しているからです。実際に、医師が直接登場して専門的な解説を行い、治療の流れや解決策を丁寧に伝えています。
そのため、視聴者は「信頼できる医療情報を安心して得られる場」として認識しやすくなっています。
まとめると、元神チャンネルは専門性とアクセシビリティを兼ね備え、タブー視されがちなテーマを親しみやすく届けている点が大きな特徴です。クリニックが自院の強みに特化して運用する際の参考になるでしょう。
べっぷ内科クリニック
べっぷ内科クリニックのチャンネルは、地域に根ざした医療情報を発信しています。生活習慣病や日常の健康管理に関する動画を提供し、患者の生活に役立つ知識を届けている点が特徴です。
なぜなら、患者が通院以外の時間にも健康を意識できるようにすることは、医療機関にとって重要な役割だからです。実際に、日常で役立つ情報を得られることで、患者との関係性が強まり、地域での信頼性が高まっています。
まとめると、教育的価値と地域医療への貢献を両立させた事例であり、地元クリニックがYouTubeをどう活用できるかを示す好例といえるでしょう。
ドクター馬場〜関東の歯医者さん〜
「ドクター馬場〜関東の歯医者さん〜」は、歯科医院によるYouTube活用の成功事例です。開設からわずか2か月で登録者数が増え、総再生数は30万回を超えるなど短期間で成果を出しています。
なぜなら、ロング動画は外注しつつショート動画は院長自らが編集し、効率的かつ継続的に発信を続けているからです。実際にこの取り組みを通じて、YouTubeを見て応募した求職者が現れるなど採用につながっただけでなく、集患にも効果が出始めています。
さらに、ジョブメドレーやグッピーといった求人媒体に依存せずに応募が集まることで、CPA(採用単価)の削減にも寄与しています。
動画を通じた継続発信が「集患」「採用」「コスト削減」の3つを同時に実現できることを示す好例であり、歯科医院のYouTube運用の可能性を広げています。
YouTube運用を成功させるための具体的ステップ |
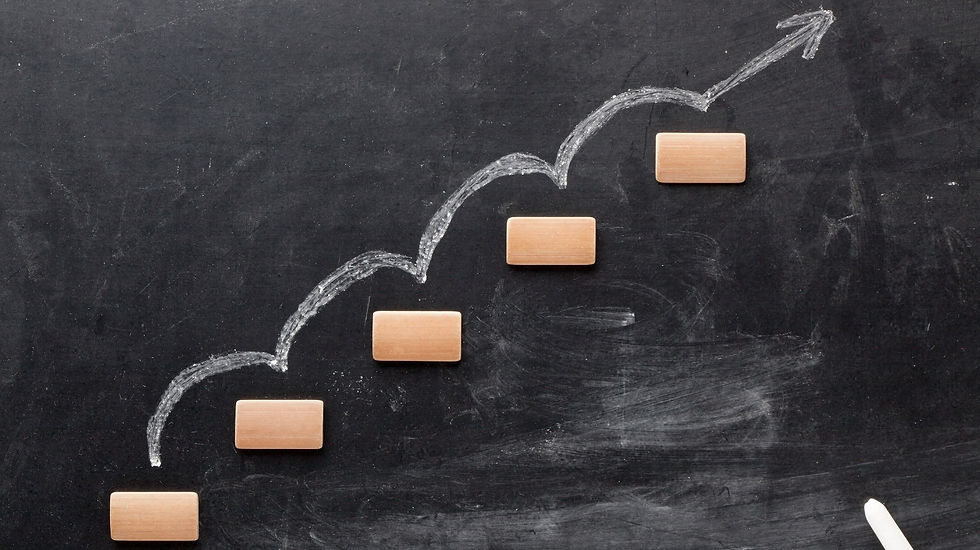
前章では、クリニックがYouTubeを運用する際に注意すべきポイントについて解説しました。
これを踏まえ、次に重要となるのは「どのように運用を進めれば成果につながるのか」という具体的な流れです。YouTube運用を成功させるには、大きく4つのステップがあります。
目的を明確にする
発信テーマを設計する
運用体制を整える
効果を検証し改善を続ける
これらを段階的に実行することで、無理のない継続運用が可能になり、集患やブランディングにもつながります。ここでは、それぞれのステップを具体的に解説していきます。
目的を明確にすることから始める
YouTube運用で最初に取り組むべきは、チャンネルの目的をはっきりさせることです。
なぜなら、「集患の強化」「ブランディング」「採用広報」など、目的によって最適な発信内容やKPIが大きく異なるからです。例えば、集患を目的とするなら治療の流れや症例紹介、採用を目的とするならスタッフのインタビューや院内の雰囲気を紹介する動画が適しています。
まとめると、動画制作に入る前に「なぜやるのか」を明確にすることで、運用の方向性がぶれず、成果につながりやすくなります。
発信テーマを設計する
目的を定めたら、次は発信するテーマを整理することが重要です。
理由として、テーマが曖昧なままでは動画の方向性が定まらず、患者にとって有益なチャンネルにならないからです。
例えば、院内紹介や治療の流れを説明する動画、医師によるQ&A形式の動画、生活習慣病予防に役立つ知識など、テーマを複数設けてシリーズ化することで継続的な発信が可能になります。
まとめると、目的に沿ったテーマを設計し、患者が知りたい情報を計画的に発信していくことが、YouTubeチャンネルの価値を高めることにつながります。
運用体制を整える
チャンネルを継続的に運営するには、体制づくりが不可欠です。
なぜなら、撮影・編集・公開・分析といった作業を属人的に進めると、途中で更新が滞りやすいからです。
例えば、院内スタッフで分担体制を作る、あるいは運用代行会社に委託するなど、継続性を前提にした仕組みを整えることが大切です。
まとめると、長期的に成果を出すためには「誰が、どの工程を、どの頻度で行うか」を明確にして、安定した運用を実現することが必要です。
効果を検証し改善を続ける
最後に欠かせないのが、公開した動画の効果を検証して改善を重ねることです。
なぜなら、どれほど良い内容でも視聴者の反応を踏まえて改善しなければ、成果を最大化できないからです。
例えば、平均視聴時間やクリック率、コメント数などを分析し、「興味を持たれる動画」「最後まで見られる動画」を探りながら修正を行います。
まとめると、データに基づいた改善を繰り返すことで、チャンネルの完成度が高まり、集患や信頼構築の効果を着実に伸ばすことができます。
外注か内製か?依頼先選びのポイント |

前章では、YouTube運用を成功させるための具体的なステップを紹介しました。
では実際に運用を進める際に、自院で対応すべきか、外部に依頼すべきかという判断に迷う方も多いのではないでしょうか。
選択肢としては「内製で運用する」「動画制作会社に依頼する」「YouTube運用代行会社に依頼する」の3つがあり、それぞれに特徴があります。
内製で運用する場合:コストを抑えられるが継続が難しいこともある
動画制作会社に依頼する場合:映像のクオリティは高いが、運用改善までは対応しないことが多い
YouTube運用代行会社に依頼する場合:戦略設計から改善まで一貫支援が可能
ここでは、それぞれの特徴を整理しながら、依頼先選びのポイントを解説します。
内製で運用する場合のメリットと課題
YouTube運用を自院で完結させる方法は、初期費用を抑えられる点で魅力的です。
なぜなら、撮影機材や編集ソフトを用意すれば、スタッフ主導で低コストに動画制作が可能だからです。
しかし、実際には専門知識や編集スキルが不足しやすく、更新頻度が下がってしまうケースも多く見られます。結果的に、視聴者に継続して見てもらえるチャンネルに育ちにくいのが課題です。
まとめると、コストを優先する場合は内製も選択肢となりますが、安定的な運用を目指すなら体制づくりとスキル習得が不可欠です。
動画制作会社に依頼する場合の特徴
高品質な映像を求めるなら、動画制作会社に依頼する選択肢があります。
理由として、撮影・編集の専門スタッフが対応するため、プロモーション映像として完成度の高い動画が得られるからです。実際に、院内紹介やリクルート用の動画を制作してブランド力を高めるクリニックもあります。
ただし、多くの制作会社は「作って納品する」ことが中心で、公開後の運用改善や効果検証までは対応していない場合が多いのが現実です。
まとめると、制作の質を重視するクリニックに適していますが、継続運用を考える場合は別途サポート体制が必要です。
YouTube運用代行会社に依頼するメリット
戦略設計から改善まで包括的にサポートしてほしいなら、YouTube運用代行会社に依頼する方法がおすすめです。
なぜなら、動画制作だけでなく、チャンネルの目的設計・企画立案・分析改善までを一貫して支援してくれるからです。
例えば、「どういう動画を作るべきか分からない」「更新を継続できるか不安」といった課題を抱えるクリニックにとって、専門知識を持つ外部パートナーは心強い存在になります。
まとめると、運用リソースが不足しているクリニックや、確実に成果につなげたい場合は、代行会社への依頼が最も有効な選択肢といえます。
また、クリニック向けのYouTube運用に対応している会社でおすすめ企業をまとめた記事がありますので、こちらも合わせて参考にしてみてください。
まとめ |

これまで、クリニックにおけるYouTube運用の重要性、メリット、事例、注意点、具体的な進め方、そして依頼先の選び方について解説してきました。
振り返ると、クリニックがYouTubeを活用すべき理由は大きく3つに整理できます。
患者に安心感を与え、信頼関係を築ける
治療内容や医師の専門性を分かりやすく伝えられる
地域や分野で他院との差別化につながる
つまり、YouTubeは「集患」「ブランディング」「採用広報」という複数の課題を同時に解決できる有効な手段です。
さらに、まだ本格的に取り組んでいるクリニックは少ないため、今から始めることで先行者優位を確保できる点も大きな魅力といえるでしょう。
動画制作や運用に不安を感じる場合は、プロに相談することで方向性を整理し、自院に最適なプランを見つけることが可能です。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。
ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するYouTube施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。
少しでも興味をお持ちの方は、下記のリンクから詳細をチェックしてみましょう。