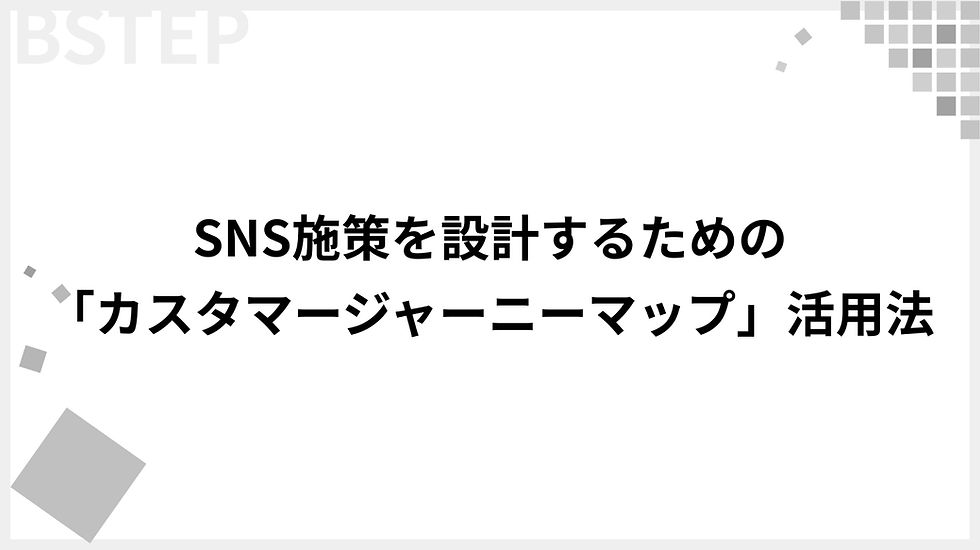【2026年最新】車屋の集客に繋がるインスタ運用を徹底解説!
- 2025年6月18日
- 読了時間: 23分
更新日:1月5日

 この記事の著者 | 山口巧己 地方×SNSマーケティングのスペシャリスト 大学在学中からSNSを独学し、父の車屋やインターンでのアウトドアブランドのSNS運用を行い、認知拡大・販売促進の向上、副次的に採用への貢献。この経験から紹介での依頼をいただき、大学4年生でフリーランスとして活動。 卒業後、WEBベンチャー企業で新規顧客開拓の営業へ従事する傍ら、フリーランス活動を継続。入社9ヶ月で退職し、独立。これまでの支援社数は50社を超える。 運用の"代行"ではなく、クライアントの経営戦略から逆算して結果へ繋げるためのSNSマーケティングが得意。 いい商品・サービス・会社を広めることが好きなSNSマーケオタク。 |
「インスタを始めてみたものの、何を投稿すれば良いのか分からない」
「バズらないと意味がないような気がして、不安になる」
「投稿を続けているのに、集客に繋がっている実感が持てない」
このようなお悩みはありませんか?
このように感じている町の車屋さんにこそ、インスタ運用を見直す価値があります。
最近の自動車業界では不正問題が続き、消費者の“信頼感”が大きく揺らいでいます。
そんな時代だからこそ、地域の車屋さんには「顔が見える安心感」が求められています。
そこで注目したいのがInstagramです。
実は、派手な投稿やバズを狙わずとも、日々の積み重ねで信頼を築き、集客につなげることができます。
本記事では、車屋がInstagramで成果を出すための考え方から、投稿設計、具体的な運用方針までを実務目線で詳しく解説しています。
なお、この記事では、弊社代表の山口が実際に父の車屋でInstagram運用を担当し、実務の中で積み上げてきた知見や工夫も交えてご紹介しています。
机上の空論ではなく、現場で試行錯誤してきた“リアル”をもとにお届けしていますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。
ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するInstagram施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。
Instagram運用でお悩みの方へ
Instagram運用で以下のようなお悩みはありませんか?
・フォロワーが増えない、エンゲージメントが低い
・投稿の内容や頻度に迷いがある
・運用を頑張っているのに売上や問い合わせに繋がらない
Instagramは多くの企業や個人が活用していますが、成果を出すためにはアルゴリズムの理解や効果的な運用戦略が欠かせません。
ビーステップでは、100アカウント以上のSNS運用支援の実績をもとに、再現性のあるInstagram運用のフレームワークを構築しています。
もし現状、Instagram運用に伸び悩みや課題がある場合は、まずはInstagramノウハウをまとめた「人気資料3点セット」を無料ダウンロードしてください。
不正問題が続く自動車業界の動向──いま、地域の車屋に求められる「信頼」 |

最近の自動車業界では、大手メーカーによる不正検査や品質偽装といったニュースが相次いで報道されています。
こうした出来事は消費者の信頼を揺るがし、業界全体のイメージにも影響を及ぼしています。
その中で、町の車屋さんにとっても他人事ではありません。
「安心して任せられるお店かどうか」が問われる時代に、地域で選ばれ続けるために必要な視点を整理します。
「企業が信じられない」今だからこそ、地域の車屋に光が当たる
自動車業界への信頼が揺らぐ中で、お客様の関心は大手メーカーから地域の販売店や整備工場へと移りつつあります。
なぜならば、大企業の名前だけでは安心できないという空気が強まり、「どんな人がやっているお店か」「ちゃんと説明してくれるか」といった“人”の信頼感を重視するようになっているからです。
たとえば、店舗での丁寧な対応はもちろん、日々の業務風景やスタッフの人柄が少しでも伝われば、「ここに任せたい」と思ってもらえる可能性が高まります。
今の時代、町の車屋さんにとっては「信頼」が最大の差別化要素であり、逆境をチャンスに変える鍵でもあるのです。
車屋にInstagram運用が必要とされる理由
自動車業界への不信感が広がるなか、地域の車屋さんが信頼を築き、選ばれ続けるには「伝える力」が必要です。
しかし、ただ店舗で丁寧な接客をしていても、その魅力が知られなければ意味がありません。
ここで注目すべきが、日々の仕事や人柄を“自然に”発信できるツール、Instagramの活用です。
この章では、Instagramを活用することの意義を、3つのポイントからお伝えします。
信頼構築につながる「人柄」が伝わる
事前接点によって「来店ハードル」が下がる
差別化・リピート促進に効果を発揮する
Instagramは、「信頼される車屋さん」になるための営業ツールです
Instagramは単なるSNSではなく、車屋さんの信頼感や雰囲気をお客様に伝える手段として活用できます。
なぜならば、文章や広告だけでは伝わりにくい“空気感”を、写真や動画を通して直感的に届けられるからです。
例えば、日々の作業風景やスタッフの笑顔、整備へのこだわりを投稿することで、「ここなら安心して任せられそう」と感じてもらえるきっかけになります。
日常の発信を通じて、お店の誠実さや信頼感が自然と伝わる。
それが、Instagramを運用する第一の価値です。
投稿が“接点”となり、来店のハードルを下げてくれる
今の時代、お客様は「いきなり行ってみる」よりも、まずネットやSNSで情報収集してから判断する傾向があります。
その理由は、初めての車屋さんに対して「ちゃんと説明してくれるか」「スタッフは親切か」といった不安があるからです。
Instagramに投稿された店舗の様子や接客の雰囲気がわかるだけで、来店のハードルはぐっと下がります。
実際に、「インスタで見たので来ました」というお客様が増えているお店もあります。
事前にお客様との接点を持てるという点で、Instagramは強力な“オンラインの入り口”になります。
発信の積み重ねが、他店との差別化につながる
町にはたくさんの車屋さんがあり、サービスや技術力にそこまで大きな差がないことも多いです。だからこそ、「どこにお願いするか」は“人”や“お店の空気”で決まることが多いのです。
たとえば、整備の様子や作業の流れ、お客様とのやりとりなどを丁寧に発信しているお店は、それだけで誠実さや安心感が伝わります。
何をしているか、どんな想いでやっているかを積み重ねて見せることで、お客様に「このお店がいい」と思ってもらえる。
その継続が、結果として他店との差別化につながっていきます。
Instagram運用の3タイプと車屋が選ぶべき型 |

Instagramを活用するといっても、運用スタイルはお店によってさまざまです。
見せ方や目的が違えば、アカウントの印象もまったく異なります。
とはいえ、町の車屋さんが成果を出すためには、「自分たちに合った型」を選び、それに沿って戦略を立てることが重要です。
この章では、代表的な3つの運用タイプを紹介しながら、どの型を選ぶべきかを明らかにしていきます。
インフルエンサー型
メディア型
店舗・ブランド型
それぞれの特性を知ることで、無理のない運用方針を組み立てることができます。
インフルエンサー型とは
インフルエンサー型とは、代表やスタッフ個人が前面に出て発信を行うスタイルです。
なぜこのスタイルが効果的かというと、「人に惹かれて来店する」ファン層を作りやすく、親近感や信頼が直接伝わるためです。
たとえば、整備スタッフが自らの言葉で車やバイクについて語ったり、趣味や日常を交えたりすることで、フォロワーが「この人にお願いしたい」と感じるケースが増えます。
ただしこの型には前提があり、発信者本人にある程度“キャラの立つ魅力”や“動画映えする雰囲気”があることが望ましいという点には注意が必要です。
さらに、軸が個人に依存する分、継続性を保つにはモチベーション維持や発信の工夫も欠かせません。
メディア型とは
メディア型は、車検やメンテナンス、購入ガイドなど、情報コンテンツをフィード投稿を中心に投稿していくスタイルです。
理由としては、「知識のあるお店=信頼できる」という印象を持たれやすく、検索性も高いため、新規のファンを獲得しやすいからです。
たとえば「エンジンオイルの交換時期」「バッテリーが上がったときの対処法」など、実用的な情報は保存・共有されやすく、長く見られる資産になります。
一方で、継続して運用するにはある程度のネタ出しや構成力が必要となるため、投稿の仕組み化がポイントになります。
店舗・ブランド型とは
店舗型は、店舗そのものやサービス内容を中心に発信していくベーシックなスタイルです。
この型が町の車屋さんに向いているのは、「人」「場所」「雰囲気」がリアルに伝わり、来店前のお客様に安心感を与えやすいからです。
たとえば、整備風景、納車時の写真、お客様の声、スタッフ紹介などを発信することで、「このお店なら大丈夫そう」と感じてもらえるきっかけになります。
町の車屋さんがInstagramを始めるなら、まずはこの店舗型をベースにするのが現実的かつ効果的な選択肢です。
\リールチェックリストやコンセプト設計シートも公開中!/
車屋がInstagram運用前に知っておきたい“現実” |

Instagramを始める前に、「理想」と「現実」のギャップを知っておくことはとても大切です。
SNS運用というと、「バズれば集客できる」「すぐに結果が出る」といったイメージを持たれがちですが、実際の運用現場ではそう簡単に成果が出るものではありません。
この章では、運用を始める前に押さえておきたいリアルな注意点を3つ紹介します。
バズらなくても集客はできる
効果が出るまでには時間がかかる
顧客層の広がりにより対応力も問われる
Instagramは継続してこそ価値が出るツールだからこそ、事前に心構えを持っておくことが成功の鍵になります。
バズらなくても集客はできる
Instagramは「バズらないと意味がない」と思われがちですが、実は必ずしもそうではありません。
なぜなら、町の車屋さんにとって重要なのは“遠くの不特定多数”ではなく、“地域の見込み客”に届くことだからです。
たとえば、日々の整備の様子やお客様の声を着実に発信していくことで、「あ、ここ見たことある」と感じた方が数ヶ月後にふらっと来店することもあります。
一見地味な投稿の積み重ねが、結果的に「信頼される店づくり」につながっていきます。
効果が出るまでには時間がかかる
SNS運用でよくある誤解が、「始めればすぐに問い合わせが来る」という期待です。
理由としては、Instagramは“信用を貯める”ためのメディアであり、短期間では成果が見えにくい構造だからです。
実際には、何ヶ月も投稿を続けてやっとDMや来店に繋がったという事例も多く、最初の数ヶ月は手応えがなくても当たり前と考えるべきです。
だからこそ、初期の段階では「数字」ではなく「発信を習慣化すること」に目標を置くと、運用が安定して続きやすくなります。
顧客層の広がりにより対応力も問われる
Instagramを通じて情報が広がることで、今までとは違うタイプのお客様と接する機会が増えてきます。
というのも、SNSは10代〜20代の若年層の利用も多く、これまで直接店舗に足を運ばなかった層からも連絡が来るようになるからです。
たとえば、DMでの問い合わせがフランクすぎたり、言葉遣いが馴れ馴れしかったりと、「これまでの常連さんとは違うな」と感じることも少なくありません。
こうした変化は一見ストレスに感じるかもしれませんが、対応を柔らかくする・一定のルールを事前に伝えるなど、工夫次第でうまく付き合っていくことができます。
新たな客層との接点として前向きに捉えることが大切です。
車屋のInstagram運用を始める前にやるべき準備 |

Instagramを始めるにあたって、最初にやっておくべき準備があります。
なんとなく投稿を始めるのではなく、「誰に」「何を」「どのように伝えるか」を整理しておくことで、運用の軸がブレず、成果にもつながりやすくなります。
この章では、車屋さんがInstagram運用を始める前に押さえておくべき7つの準備項目をご紹介します。
目的・目標の設定
自社の強み/弱みの整理
ターゲットの明確化
コンセプトの設定
プロフィールの設計
発信内容の設計
効果測定の考え方
この土台をしっかり整えることが、Instagram運用成功への第一歩です。
目的・目標の設定
Instagram運用は、まず「何のためにやるのか」「どんな結果を目指すのか」を明確にすることが重要です。
なぜなら、目標が曖昧なままだと、発信内容も方向性が定まらず、成果が見えにくくなるからです。
たとえば「月に5件の問い合わせを目指す」「まずはフォロワー100人を達成する」など、数字を交えた現実的なゴールがあると、行動にも一貫性が生まれます。
ゴールが定まっていれば、途中で迷ったときも判断基準ができ、継続しやすくなります。
自社の強み/弱みの整理
Instagramで効果的に情報発信をするには、まず自分たちの「強み」と「弱み」を正しく把握することが欠かせません。
というのも、強みを理解していなければアピールが曖昧になり、弱みを知らなければ間違った発信につながってしまうからです。
たとえば「アットホームな接客」が強みであれば、それが伝わるようなスタッフの日常や会話風景の投稿が有効です。
一方で「価格で勝負できない」なら、価値を言語化する投稿でカバーする必要があります。
自社を客観的に見つめ直すことが、Instagramの発信に説得力を持たせてくれます。
ターゲットの明確化
誰に向けて発信するのかを決めることは、投稿の方向性を定めるうえで非常に重要です。
なぜなら、年齢・性別・車の用途などによって、響く言葉や見せ方がまったく変わるからです。
たとえば、20代の若者を狙うなら、親しみやすい言葉やストーリーズでのクイズなどが有効ですし、ファミリー層が対象なら、「チャイルドシート取り付け相談OK」など、安心を訴求する内容が求められます。
もちろん「お金を払ってくれるなら誰でもウェルカム」という考え方もあると思います。
ただ、それは広告費や人員を潤沢に持つ大手企業だからこそ成り立つやり方です。
町の車屋さんのように限られたリソースで運用する場合は、最も成果につながりやすい層=“優先すべきターゲット”を明確にすることが、運用の無駄を省き、効果を最大化するコツになります。
コンセプトの設定
Instagramアカウントの“方向性”を決めるうえで欠かせないのがコンセプト設計です。
なぜなら、投稿内容や見せ方に一貫性がなければ、フォローされづらく、信頼にもつながりにくいからです。
たとえば、「技術力を前面に出す」「親しみやすさを打ち出す」「おしゃれで若い層に寄せる」など、コンセプトをひとつに絞ることで、投稿のトーンやビジュアル、言葉選びまで統一できます。
見た人が一瞬で「このお店はこういう雰囲気」と理解できるようになることが、集客においても大きな力になります。
プロフィールの設計
Instagramで最初に見られるのがプロフィール欄です。
ここが“店舗の顔”とも言えるため、設計には特に注意が必要です。
というのも、プロフィール次第で「ここに問い合わせてみよう」と思ってもらえるかどうかが決まるからです。
たとえば、店舗名・場所・対応サービス・問い合わせ方法・営業時間などは必ず明記し、さらにハイライト機能を使って「事例集」や「アクセス案内」を固定しておくと安心感が生まれます。
投稿よりも先に見られる場所だからこそ、信頼される情報設計が大切です。
発信内容の設計
どんな投稿をしていくかを事前に設計しておくことで、投稿が止まるリスクを大きく減らすことができます。
理由は、ネタ切れや方向性のブレを防ぎ、継続しやすい体制を整えることができるからです。
たとえば、「作業風景」「車・バイクの紹介」「スタッフの一言」「お客様の声」「Q&A」「よくある質問」「Googleマップレビュー紹介」など、投稿ジャンルを先に決めておくと、迷わず投稿できます。
発信は“気分”ではなく“仕組み”で回すことで、無理なく続けられるようになります。
効果測定の考え方
Instagram運用の成果は、最初のうちは数字に表れにくいため、適切な視点で測ることが求められます。
というのも、フォロワー数や「いいね」だけで一喜一憂していると、本質的な改善につながらないからです。
たとえば、「来店時にInstagramを見ていたかを聞く」「DM問い合わせの経路を記録する」といったリアル接点でのヒアリングこそが、もっとも確かなデータになります。
\リールチェックリストやコンセプト設計シートも公開中!/
車屋における売上最大化のための考え方と発信設計 |

Instagram運用の目的は、フォロワーを増やすことではなく、最終的には売上につなげることです。
そのためには、ただ投稿を続けるだけでなく、「売上が生まれる流れ」を意識した設計が欠かせません。
この章では、車屋さんがInstagramで成果を出すための考え方として、次の2つの要素に注目して解説します。
認知率を上げる投稿
選ばれる確率(プレファレンス)を上げる工夫
その前提として、まずは「売上をつくる仕組み」について、共通の理解を持っておきましょう。
売上最大化のための考え方とは
Instagramを売上につなげるためには、「なんとなく投稿する」のではなく、売上がどう生まれるかという構造を理解した上で運用することが重要です。
そのとき参考になるのが、次の公式です。
売上=認知率×配荷率×選ばれる確率(プレファレンス)
これは本来、マーケティングの現場で商品を売る際によく使われる考え方です。
「認知率」はその商品や店舗を知っている人の割合、「配荷率」は商品が実際に店頭などで購入できる状態にある割合、そして「選ばれる確率(プレファレンス)」は、複数の選択肢の中から自社を選んでもらえる割合を指します。
たとえば、車屋さんで言えば、実際に車検や修理の予約を何件受けられるか、1日あたり何組のお客様を対応できるかといった「受け皿のキャパシティ」が配荷率にあたります。
どれだけInstagramで認知が広がったとしても、物理的に予約を受けられる枠が少なければ、売上にはつながりません。
また、「対応できる車種」「メニュー構成」「営業時間帯」などが、お客様のニーズと合っているかどうかも、配荷の“質”に関わる重要な視点です。
ただし、Instagram運用においては、この「配荷率」を直接コントロールすることはできません。Instagramはあくまで「認知を広げる」「選ばれる理由をつくる」ためのマーケティングツールです。
つまり、3要素のうち、運用によって影響を与えられるのは認知率と選ばれる確率の2つに絞られるということです。
だからこそ、限られたリソースで運用する町の車屋さんには、まずこの2つに集中した設計がもっとも成果に直結するアプローチだと言えます。
認知率を上げる投稿とは
まず大切なのは、お店の存在を知ってもらうことです。というのも、お客様の多くは「そもそもこのお店を知らない」という段階からスタートしているからです。
たとえば、整備作業の様子を撮影したリール動画、バイクのマフラー音やカスタム紹介などのエンタメ要素のある投稿、ちょっとした豆知識や裏話などは、新しい人に届きやすく、認知度を高めるのに効果的です。
「まずは知ってもらう」ための投稿は、フォロワー数よりも“リーチ数”を意識して発信すると効果が見えやすくなります。
選ばれる確率(プレファレンス)を上げる工夫
お店を知ってもらったあと、次に大切なのは「他ではなく、このお店を選ぶ理由」を伝えることです。
なぜなら、車の購入や整備は高額で失敗できない買い物であり、安心感と信頼感が決め手になるからです。
たとえば、お客様の声や納車時の写真、店舗の内外観の紹介、スタッフの紹介、対応事例などは、「このお店なら任せられそう」と感じてもらう材料になります。
さらに、ハイライトに「よくある質問」や「店舗までの行き方」をまとめておくと、来店前の不安を自然に取り除くことができます。
安心して相談できる、頼れる存在だと伝えることが、最終的な来店や契約へとつながっていきます。
車屋のInstagram運用における具体的な投稿内容 |

Instagramで成果を出すには、「どんな投稿を、どんな目的で行うか」を明確にしておくことが欠かせません。
日々なんとなく投稿するのではなく、「認知を広げたいのか」「信頼を得たいのか」といった狙いに応じて内容を設計することで、限られた投稿でもしっかり成果につなげることができます。
この章では、目的別におすすめの投稿内容をご紹介します。
認知を広げる投稿
選ばれる理由を伝える投稿
この2つの目的を押さえて発信すれば、「なんとなく投稿」から一歩抜け出すことができます。
認知を広げる投稿
お店の存在を知ってもらうためには、拡散性が高く、目に留まりやすい投稿を意識することが大切です。
というのも、認知段階では「まだフォローされていない人」への接触が必要だからです。
たとえば、整備やカスタムの様子を撮影したリール動画、車やバイクのマフラー音、オイル交換や洗車のビフォーアフター、トレンドに乗ったリール音源やスタンプの活用などは、比較的リーチが伸びやすく認知拡大に役立ちます。
これらは日常業務の延長で撮れることが多く、無理なく続けられるのもポイントです。
選ばれる理由を伝える投稿
「知ってもらったあと」は、「他のお店ではなく、うちにお願いしたい」と思ってもらえるかどうかが勝負になります。
なぜなら、車検や整備、購入といった高額なサービスでは、最終的に“安心して任せられるかどうか”が意思決定を左右するからです。
たとえば、納車事例やお客様の声、店内の雰囲気、スタッフ紹介、整備のこだわり、Googleマップの口コミ紹介、Q&A形式の投稿などは、信頼感を高めるのに効果的です。
さらに、これらをハイライトで整理しておくことで、プロフィールを訪れた人にも安心感が伝わります。
日々の発信を通して「ここなら大丈夫そう」と思ってもらえるようにすることが、来店につながる鍵になります。
\リールチェックリストやコンセプト設計シートも公開中!/
車屋がやるべきInstagram投稿・運用方針(頻度・役割・対応ルールなど) |

Instagram運用で成果を出すには、投稿内容を工夫するだけでなく、投稿頻度・役割分担・対応のルールをあらかじめ決めておくことが重要です。
というのも、「ネタが尽きた」「投稿が止まった」「お客様対応が雑になった」といった問題は、運用設計の甘さから起きることが多いからです。
この章では、投稿ジャンルごとに具体的な頻度や役割、対応ルールのポイントを整理します。
リール
フィード
ストーリーズ
タグづけ対応
この4点を押さえることで、無理なく長く続けられる運用体制が整います。
リール
リールは、Instagram内で最も拡散力のあるフォーマットです。
理由は、非フォロワーにも届く「おすすめ表示」枠に乗りやすく、認知拡大に直結しやすいからです。
投稿頻度としては、3~4日に1回、月あたり8〜12本程度を目安にできると理想的です。
作業の様子やビフォーアフター、エンタメ要素を含んだ短尺動画などは、編集が少なくても効果的に届けられます。
まずはスマホ1台で始められる範囲から、無理のない範囲で数をこなすことが重要です。
フィード
フィード投稿は、「アカウントを訪れたときの第一印象」をつくる役割を持ちます。
なぜなら、プロフィールを見に来たユーザーは、投稿一覧からお店の雰囲気や信頼感を判断するからです。
運用初期には9〜12投稿を一気に整備して、店舗の強みや雰囲気を伝える基盤を作りましょう。
その後は最低でも月1回の投稿を目指し、できるタイミングで柔軟に追加していくスタイルで問題ありません。
投稿デザインはテンプレート化しておくと、投稿ごとの作業負担が軽減され、継続しやすくなります。
ストーリーズ
ストーリーズは、日常的な接点をつくり、「今営業している」「活動している」という“安心感”を届けるのに最適な機能です。
理由は、フォロワーにとっての“習慣的な接触点”になりやすく、営業感を出さずに信頼感を醸成できるからです。
基本は毎日更新が理想です。
以下のように、時間帯に応じた発信を設計すると無理なく続けられます。
朝:営業前の雰囲気(「開店しました」は不要。更新だけで営業中と伝わる)
昼:整備や作業の様子
夜:終了の報告(「閉店しました」は避け、「今日もお疲れさまでした」など自然な表現を)/投稿共有/クイズ系
休業日は「本日はお休みです」と伝えるだけで信頼感アップ
スタンプ・GIFの活用も忘れずに。見ていて楽しい“動きのあるストーリー”を心がけましょう。
タグづけ対応
Instagramでは、お客様が投稿にお店をタグづけしてくれることがあります。
このときの初動対応が関係構築のチャンスになります。
なぜなら、タグづけはお客様の“好意”による無料PRであり、それに対して丁寧に反応することで、ファンとしての定着につながるからです。
最初のうちは、必ずお礼のDMを送るようにしましょう。
タグづけが頻繁になってきたら、スタンプ付きの返信やストーリーでのシェアなどでも十分効果があります。
日々のこうした小さな対応が、ブランドの印象に直結します。
車屋なら必ずやっておきたい3つのアクション |

Instagram運用では、投稿やフォロワー数だけに注目しがちですが、実は“日々の接客の中でできるちょっとした工夫”が成果に直結することも少なくありません。
この章では、車屋さんがInstagramを通じて集客力を高めていくうえで、必ずやっておきたい3つのアクションをご紹介します。
「何がきっかけで知ったか」をヒアリングする
Googleマップのレビュー依頼を行う
Instagram投稿への掲載許可を取る
どれもすぐに実践できて効果が見込める、地に足のついた施策です。
「何がきっかけで知ったか」をヒアリングする
Instagram経由で来店されたかどうかを把握するには、お客様に直接聞くのが一番確実な方法です。
なぜなら、SNS経由の集客は数値に出にくく、Instagram内のデータだけでは“誰が何を見て来店したのか”まではわからないからです。
たとえば、受付や会話の中で「当店を知ったきっかけは何でしたか?」と自然に聞くようにすれば、Instagramの投稿がどれだけ届いているかの“生の声”が蓄積されていきます。
このデータが増えれば、「どの投稿が反応を生んだのか」「どう改善すべきか」といった判断もしやすくなります。
Googleマップのレビュー依頼を行う
レビューは、Instagramと並行して信頼を築くために欠かせない要素です。
というのも、多くのお客様はSNSだけでなくGoogle検索や地図アプリで情報を確認し、口コミを参考にして来店を決めるからです。
たとえば、来店や納車の際に「よければGoogleマップのクチコミもお願いできると嬉しいです」と一声かけるだけでも、少しずつレビューが集まります。
実際にレビューの内容をInstagramで紹介すれば、SNSとGoogleの両方で相乗効果が生まれます。
Instagram投稿への掲載許可を取る
お客様との関係性を築きながら、自然にInstagramの存在を伝える方法として効果的なのが、「投稿してもいいですか?」という一言です。
なぜこれが効果的かというと、ただ宣伝するのではなく、お客様に“関わっていただく”ことで、Instagramの存在そのものを印象づけられるからです。
たとえば、「納車の記念に、もしよければ写真を撮らせてください。Instagramに載せても大丈夫ですか?」と伝えることで、お客様にも喜ばれやすく、同時に他のユーザーへの安心感にもつながります。
掲載許可はPRのきっかけであると同時に、“信頼の延長線”にある行為でもあります。
車屋のインスタ運用で集客を行うならビーステップへ! |

ここまで、Instagramを活用した車屋さんの集客・信頼構築のポイントについて、業界動向から実践的な投稿・運用方法まで幅広くお伝えしてきました。
今、自動車業界全体が信頼の再構築を求められている中で、地域の車屋さんこそが“顔の見える安心感”を届けられる存在として注目されています。
そして、その信頼を可視化し、じわじわとお客様との関係性を深めていけるツールが、まさにInstagramです。
Instagramを活用すれば、
認知の獲得
信頼の構築
リピーターや紹介の増加
といった導線を、無理なく自然なかたちで作ることができます。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。
ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するInstagram施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。