SNSブランディングとは?戦略から設計のための6ステップを徹底解説!
- 株式会社ビーステップ
- 2025年9月17日
- 読了時間: 29分
更新日:1月13日

 この記事の著者 | 山口巧己 地方×SNSマーケティングのスペシャリスト 大学在学中からSNSを独学し、父の車屋やインターンでのアウトドアブランドのSNS運用を行い、認知拡大・販売促進の向上、副次的に採用への貢献。この経験から紹介での依頼をいただき、大学4年生でフリーランスとして活動。 卒業後、WEBベンチャー企業で新規顧客開拓の営業へ従事する傍ら、フリーランス活動を継続。入社9ヶ月で退職し、独立。これまでの支援社数は50社を超える。 運用の"代行"ではなく、クライアントの経営戦略から逆算して結果へ繋げるためのSNSマーケティングが得意。 いい商品・サービス・会社を広めることが好きなSNSマーケオタク。 |
SNSで定期的に投稿しているけれど、それがブランドの成長につながっている実感がない──。
そんな違和感や疑問を抱えていませんか?
「とりあえず更新はしているけど、それで十分なのか?」
とSNSを広報の一部としてなんとなく続けている方もいれば、
「投稿に統一感がない」
「ブランドらしさが出せていない」
と感じている方もいるでしょう。
中には、「CMや広告とSNSの印象がバラバラで、ユーザーに誤解されている気がする」といった、深刻な課題を抱えている方もいるかもしれません。
今やSNSは、消費者にとって日常的な情報収集ツールであり、企業の印象形成に大きく影響を与えるメディアです。ビジュアルや投稿内容を工夫しているのにブランドが伝わらないとしたら、それはブランド設計という“土台”が曖昧になっているからかもしれません。
本記事では、SNSブランディングを成功させるための設計ステップから、世界観を一貫して伝えるための運用・評価方法までを詳しく解説します。
SNSで“伝わるブランド”を育てたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
ブランディングについての記事は、以下の関連記事も併せてご覧ください。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。
ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するSNS施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。
目次
SNS利用率の高さと消費者行動の変化
企業が無視できないSNSの影響力
SNSはブランドの“顔”になる
重要なのは「世界観」の統一
各プロモーション施策の方向性を明確にする
SNS運用にブランドガイドラインを活用する
世界観が伝わると「ブランドらしさ」が定着する
逆に一貫性がないと起こる3つの失敗
ブランディングとは?SNSとの関係性を再整理する |
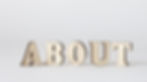
SNSブランディングの重要性を深く理解するためには、そもそも「ブランディング」とは何か、その基礎を押さえておく必要があります。
多くの企業がSNSを活用する中で、ブランドイメージやトーンにばらつきが出る原因は、根本となるブランド戦略が明文化されていない、または現場まで浸透していないことにあります。
本章では、ブランディングの基本的な考え方と、SNSとの関係性を理論的に整理します。
これから取り上げる3つの概念は、SNS運用の現場にも大きく関わるポイントです。
ブランドアイデンティティとブランドイメージの違い
カテゴリエントリーポイント(CEP)の考え方
SNSが“ブランド接点の最前線”である理由
SNSを戦略的に活用するために、まずはこれらの視点からブランディングの基盤を確認していきましょう。
ブランドアイデンティティとブランドイメージの違い
ブランドアイデンティティとは、企業やブランドが「こう見られたい」と意図して定めた価値やメッセージのことです。これに対して、ブランドイメージは、実際に消費者が感じ取っている印象や感情を指します。
この2つの間にギャップがあると、SNSや広告でどれだけ発信しても、受け手には本来の意図が伝わりません。SNS運用では特に、日々の投稿がブランドイメージに直結しやすいため、アイデンティティに沿った表現になっているかを常に確認する必要があります。
一貫性のあるSNS運用とは、アイデンティティを軸に、ユーザーに届けたい印象を意図的に設計し、ブレずに発信し続けることなのです。
カテゴリエントリーポイント(CEP)の考え方
CEP(カテゴリエントリーポイント)は、消費者が商品やサービスを思い出す“きっかけ”となる状況や場面を意味します。
たとえば、「夏のレジャー」と聞いて「テーマパーク」を思い出す、「特別な記念日のレストラン」と聞いて「ホテルレストラン」が浮かぶ、といったように、ある場面やニーズから特定のブランドが連想される状態を目指します。
SNSは、こうしたCEPを“具体的な投稿”として具現化できる場でもあります。たとえば、ユーザーが「週末のお出かけ先」を探しているときに、「非日常感が味わえる空間」を投稿で伝えられれば、その瞬間にブランドがCEPとして想起される可能性が高まります。
SNSの投稿設計において、「この投稿はどのCEPを刺激しているか?」を意識することで、ブランド想起率の向上につながります。
SNSが“ブランド接点の最前線”である理由
現在、多くの消費者が商品やサービスを検討する際に、まずSNSをチェックするという行動が定着しています。そのため、SNSはもはや広告やWebサイトの“補足チャネル”ではなく、ブランドとの初接点となる最前線なのです。
SNSでは、視覚的な印象、言葉のトーン、ユーザーとのやりとりまですべてがブランドイメージを形成します。つまり、ブランドアイデンティティとユーザーに伝わるブランドイメージが一致しているかを、最も敏感に反映するのがSNSという場なのです。
だからこそ、SNSブランディングは単なる投稿スケジュールの管理ではなく、「ブランドのコアを、日々の発信で体現する」行為だと認識する必要があります。
なお、ブランディングの基本的な考え方や構築の進め方については、以下の記事でより詳しく解説しています。
SNS戦略を立てる前に、ブランドの軸を再定義したい方はぜひご参照ください。
SNSは現代の情報収集ツール |

企業がブランドを構築・発信するうえで、今やSNSの存在を無視することはできません。
特に、スマートフォンが生活に浸透したことで、消費者はいつでもどこでもSNSを通じて情報を得る時代になりました。
これから紹介するように、SNSは消費者行動の中核を担うツールとして定着しており、企業にとってもその重要性は年々高まっています。
本章では、SNSが現代の情報収集手段としてどのような役割を果たしているのか、主に2つの視点から解説します。
SNSの利用率の高さと消費者行動の変化
企業が無視できないSNSの影響力
これらの内容を通じて、SNSがブランディング戦略においてどれほど重要な存在かを明確にしていきます。
SNS利用率の高さと消費者行動の変化
SNSは今や、幅広い年齢層で当たり前のように利用されており、その利用率は年々増加しています。
このような状況の中で、消費者の情報収集行動にも大きな変化が起きています。従来はGoogleなどの検索エンジンが主流だった情報収集手段は、今ではSNS検索へとシフトしつつあります。特に若年層においては、InstagramやX(旧Twitter)、TikTokで「リアルな口コミ」や「使用感」をチェックする行動が定着しているのが特徴です。
つまり、SNSは単なる交流の場ではなく、「購入前の確認ツール」としての役割を果たしており、企業やブランドがその中でどう映っているかが、購買判断に直結する時代になっているのです。
企業が無視できないSNSの影響力
SNSの影響力は、もはやマーケティング施策の一部に留まらず、企業の評価や信頼性そのものに大きく関わるレベルにまで拡大しています。
なぜならば、SNSにはユーザーが自発的に投稿したコンテンツ、いわゆるUGC(UserGeneratedContent)が大量に存在しており、これらは消費者にとって広告よりも信頼されやすい情報源となるからです。
たとえば、ある化粧品ブランドがテレビCMで好印象を与えたとしても、SNS上に「実際は効果を感じなかった」「対応が悪かった」といった投稿があれば、そのネガティブな声はブランド全体に悪影響を及ぼしかねません。逆に、ユーザーから高評価の声が集まれば、それだけで企業に対する信頼感が高まり、口コミによる新たな顧客獲得も期待できます。
このように、SNSは企業側の発信だけでなく、ユーザーの声によってもブランド価値が左右される場であり、戦略的に活用しなければ大きな機会損失につながるのです。
SNS時代に求められるブランディング |

前章では、SNSが現代において情報収集の主要な手段となっており、企業活動に与える影響も非常に大きいことを解説しました。
こうした環境下においては、単に「SNSを活用する」だけでなく、企業がどのような世界観や価値観をSNS上で表現するかが問われています。
つまり、SNSはブランドの在り方そのものを映し出す鏡になっているのです。
本章では、SNS時代に必要なブランディングの考え方として、以下の2点を解説します。
SNSはブランドの“顔”になる
重要なのは「世界観」の統一
SNSチャネル別に異なる“世界観”の表現方法
これらを踏まえて、現代のブランディングにおけるSNSの役割と、それに伴う課題や注意点を掘り下げていきます。
SNSはブランドの“顔”になる
SNSは、いまやブランドと消費者をつなぐ最前線です。理由としては、企業のSNSアカウントが、広告や店舗に触れる前に「はじめて接点を持つ場所」になっているからです。
特に若年層においては、まずInstagramやXなどのSNSでブランドを検索し、ビジュアルや投稿内容、返信対応などから「どんなブランドなのか」を判断する傾向が強くなっています。
たとえば、あるファッションブランドが洗練されたイメージを持っていても、SNS投稿が雑で、対応が無機質だった場合、ユーザーはブランドに対してネガティブな印象を持つかもしれません。
逆に、日常的なやりとりや投稿が丁寧であれば、それだけでブランドに親近感や信頼感を抱くユーザーも多いでしょう。
つまり、SNSは単なる販促チャネルではなく、「企業の顔」としての役割を果たしており、その表現や対応すべてがブランディングに直結しているのです。
重要なのは「世界観」の統一
ブランドとしての印象を確立するには、SNS上でも一貫した世界観が必要不可欠です。その理由は、ユーザーが複数のチャネルでブランドに触れる中で、もしメッセージやビジュアル、トーンにズレがあると、ブランドの信頼性が損なわれてしまうからです。
例えば、テレビCMでは華やかで上質な世界観を演出しているのに、SNSではカジュアルすぎる口調や雑多なビジュアルで運用されていた場合、ユーザーはそのギャップに違和感を抱きます。結果として、どんな価値を届けたいブランドなのかが曖昧になり、ブランディングが機能しなくなってしまうのです。
このような事態を防ぐには、あらゆるチャネルで“軸の通った世界観”を貫くことが求められます。SNSにおいても、投稿のトーンやコンテンツのビジュアル、タイポグラフィーに至るまで、ブランドの本質を反映した表現が徹底されているかが、ユーザーとの信頼関係を築くための重要なポイントとなります。
実際に、テレビCMやプロモーション動画で訴求している世界観が、SNS上で十分に再現されていないケースも見受けられます。
例えば「ザストリングス博多」では、映像広告でスタイリッシュで洗練された雰囲気を打ち出している一方で、Instagramの投稿にはその軸が必ずしも反映されているとは言い切れません。
(Youtube差し込み)
それぞれの投稿における「誰に・何を伝えたいのか」が不明瞭で、CMとの印象のギャップを感じさせてしまう可能性があります。
SNSが消費者との“初接点”になる今、世界観の一貫性が欠けると、せっかくのプロモーションがブランドイメージとして定着しづらくなります。
SNSチャネル別に異なる“世界観”の表現方法
SNSとひとくちに言っても、各プラットフォームには異なる文化やユーザー特性が存在します。そのため、すべてのチャネルで同じコンテンツを発信しても、必ずしも効果的とは限りません。重要なのは、それぞれのチャネルの特性を理解し、世界観を“最適な形で”表現する工夫です。
たとえば、Instagramはビジュアル中心のSNSであり、ブランドの世界観を写真や動画で魅せるのに適しています。統一された色使いや、丁寧な構図、フィード全体のトーンに一貫性があると、ユーザーに視覚的な心地よさを提供できます。
一方、X(旧Twitter)はリアルタイム性と“言葉”の影響力が強く、時事性やブランドの姿勢・考え方を発信するのに適しています。ここでは、世界観そのものというよりも、ブランドの思想やスタンスを表現することで、共感を得られる投稿が生まれやすくなります。
TikTokでは、動きとテンポ感のある動画が主流で、視覚・聴覚のインパクトで世界観を伝える必要があります。短い時間でメッセージを届けるため、ブランドの“体験価値”を直感的に伝えることが重要になります。
このように、SNSごとに「世界観の表し方」が異なる以上、同じアイデンティティを軸にしながらも、表現手法は柔軟に変える必要があります。ただし、コアとなる価値やトーンがブレないことは大前提です。
つまり、SNSブランディングでは「統一」と「最適化」のバランスが求められます。どのチャネルでも同じように見えることが正解ではなく、“そのSNSらしさ”を活かした表現の中に、ブランドの芯を感じさせることが、ユーザーの共感と信頼を育む鍵となります。
SNSとその他プロモーションの一貫性を保つには |

前章では、SNS上でもブランドの世界観やトーンを統一することの重要性について解説しました。
しかし、ブランディングを成功させるためには、SNSだけでなく、テレビCM・Web広告・リアルイベントなど、他のプロモーション施策との一貫性も欠かせません。
どこでブランドに触れても同じ印象を与えられるようにすることが、ユーザーにとっての安心感や信頼感につながります。
本章では、以下の2つの観点から、プロモーションの統一性を実現するためのポイントを紹介します。
各プロモーション施策の方向性を明確にする
SNS運用にブランドガイドラインを活用する
SNS世界観統一のためのチェックポイント
これらの対策を講じることで、チャネルごとに表現がブレることなく、ブランドの“芯”を伝えることができるようになります。
各プロモーション施策の方向性を明確にする
ブランドの世界観を統一するためには、まずすべてのプロモーション施策において「目指す方向性」を明確にすることが重要です。
なぜなら、テレビCMやSNS、Web広告、店舗での販促施策など、チャネルごとに担当者や制作パートナーが異なることが多く、それぞれが独立して動いてしまうと、ブランドの軸がぶれてしまうからです。
たとえば、テレビCMでは「上質・高級感」を打ち出しているにも関わらず、SNSではカジュアルな言葉遣いやポップなビジュアルを多用していた場合、ユーザーはブランドに一貫性を感じられず、混乱してしまいます。
その結果、ブランドがどのような価値を提供しているのかが曖昧になり、共感や支持を得にくくなってしまうのです。
すべての施策において、「誰に・何を・どのように届けるのか」という軸を明確にし、それを全体で共有することで、各プロモーションの表現が自然と統一され、ブランディングが強化されていきます。
SNS運用にブランドガイドラインを活用する
SNSでの世界観を守るためには、ブランドガイドラインをSNS運用にしっかりと適用することが有効です。というのも、SNSはスピード感が重視される場であるため、投稿内容やデザインの判断が個人の裁量に委ねられがちです。その結果、投稿ごとにトーンや雰囲気にズレが生じ、ブランディングが崩れてしまうリスクがあります。
そこで必要になるのが、ブランドガイドラインの活用です。ブランドカラーやロゴの扱い方、フォントの種類、画像の選定基準、トーン&マナー、さらにはコメント対応時の語調など、細部にわたるガイドを設けることで、SNS投稿の一貫性を維持できます。
実際に、大手企業の多くはSNS専用の運用ガイドラインを整備しており、それを社内・外部パートナーと共有することで、ブランドの価値を損なうことなく継続的な発信を可能にしています。
SNSは一度投稿されると削除や修正が難しいメディアだからこそ、事前のルール設計がブランディングの安定性を支える鍵となるのです。
また、「ジャングリア沖縄」のように、既に大規模な広告やメディア露出で認知が広がっているブランドであっても、SNSにおける世界観の統一は欠かせません。
(Instagram差し込み)
コンセプトとして掲げている「PowerVacance!!」のイメージに対して、実際のSNS投稿では“情報優先”の内容が多く、世界観としての一貫性はやや弱く映ってしまう印象を受けます。
色使いやトンマナに一定の統一感はあるものの、SNSで発信するコンテンツにコンセプトが落とし込まれていなければ、ユーザーはその世界観を感じ取ることができません。
SNS世界観統一のためのチェックポイント
SNSでブランドの世界観を一貫して伝えるためには、感覚的に「らしさ」を表現するだけでは不十分です。実際には、投稿に含まれる要素一つひとつにおいて「ブランドとして適切か?」を検証する視点が求められます。
ここでは、SNS運用担当者が投稿前に確認すべき基本的なチェックポイントを紹介します。毎回すべてを意識するのは難しくとも、最低限以下の視点が揃っていれば、SNSにおけるブランドの印象は安定しやすくなります。
1.投稿のトーンや語尾が一貫しているか
語尾や表現方法がバラついていると、発信者が複数いてもユーザーには“中の人”が見えず、ブランドの人格を感じにくくなります。「です・ます」なのか、くだけた口調なのか、文体ルールは統一しましょう。
2.写真や画像の雰囲気に統一感があるか
フィルター、光の当て方、背景処理、撮影角度など、細かな部分のスタイルが統一されていれば、フィード全体に「世界観」が滲み出ます。投稿単体でなく、アカウント全体としてのビジュアルの連続性を意識しましょう。
3.ハッシュタグにルールや意図があるか
なんとなく毎回変えるのではなく、ブランドに紐づいた固定ハッシュタグや、定番キーワードを一定の基準で活用しましょう。ユーザーが検索・発見しやすくなるだけでなく、投稿の意味合いも伝わりやすくなります。
4.プロフィール文・アイコン・リンクも世界観と合致しているか
投稿だけでなく、プロフィールも重要なブランド表現の一部です。「誰に、何を届けているのか」「どんな価値を提供しているのか」が明確に伝わる内容になっているかを見直しましょう。
5.他チャネルと表現が食い違っていないか
テレビCM、Webサイト、LP、チラシなど、他のプロモーション施策とトーンがズレていないかを定期的に確認することも大切です。SNSだけが浮いて見える状態になっていないか、第三者の目線でチェックしましょう。
このように、SNS投稿のチェック体制を整えることで、運用担当者ごとに品質や方向性がブレることを防げます。
ルールを定めすぎると表現の自由度が下がるリスクもありますが、最低限の“軸”を全員が共有することは、ブランド価値を守る上で非常に重要です。
世界観の一貫性がブランドの信頼と共感を生む |

前章では、SNSと他のプロモーション施策との間で一貫した表現を保つためのポイントについて解説しました。
ブランドが複数のチャネルで接点を持つ現代において、「どこで見ても同じ印象が伝わる」ことは、信頼獲得の基本とも言えます。
この章では、ブランドの世界観を一貫させることで得られる効果と、それが欠けた場合に起こる失敗のパターンについて、以下の2つの視点からお伝えします。
世界観が伝わると「ブランドらしさ」が定着する
逆に一貫性がないと起こる3つの失敗
ブランディングを成功させるには、統一された表現を「やり続ける」ことが鍵になります。
世界観が伝わると「ブランドらしさ」が定着する
ブランドに対する認識は、一度の広告やキャンペーンで定着するものではありません。
なぜなら、ユーザーは多くの情報に日々触れており、その中で印象に残るブランドは、「自分の価値観と一致する」と感じられる、一貫したメッセージを発信し続けている存在だからです。
たとえば、あるブランドが一貫して「ミニマルで上質なライフスタイル」を提案している場合、SNS投稿・Webサイト・広告・店舗の雰囲気すべてがその価値観を表していれば、ユーザーは自然と「そのブランドらしさ」を感じ取るようになります。
この“ブランドらしさ”は、ロゴや商品そのもの以上に、ユーザーの記憶に残る要素となり、購買やファン化の後押しになります。
つまり、世界観を貫くことによって、ブランドは単なる企業名や商品名ではなく、「共感される存在」としてユーザーの心に根付くのです。
逆に一貫性がないと起こる3つの失敗
ブランドに一貫性がないと、ユーザーの中でブランドに対する評価や印象が曖昧になります。
なぜかというと、異なるチャネルで矛盾したメッセージや表現に触れることで、ユーザーは「何を信じていいかわからない」と感じてしまうからです。
このような場合に起こりやすい失敗には、以下のようなものがあります。
世界観のバラつきによる「迷い」
ユーザーがブランドの価値や対象層を正確に理解できず、選ばれにくくなる。
SNS投稿だけが浮いてしまう「違和感」
他のプロモーションとトーンが異なるため、ブランドの一部として機能しない。
意図しないブランドイメージの「拡散」
SNSでの表現が誤解を招き、ブランド本来の方向性とは異なるイメージが広まる。
一度ズレた世界観は、ユーザーの中で誤解として定着してしまう可能性があるため、日々の発信や運用のなかで表現の精度を保つことが重要です。
ブランドを育てていくうえでは、単に情報を発信するのではなく、「どう伝えるか」「どう見せるか」にまで意識を向ける姿勢が欠かせません。
SNSブランディングを成功させるための6つのステップ |

SNSでブランドの世界観を正しく伝えるには、クリエイティブや投稿の工夫だけでは不十分です。
重要なのは、SNSに何を投稿するかではなく、その“芯”となるブランドの価値やキャラクターをどう設計するか。
この設計が曖昧なまま運用を始めると、投稿に一貫性がなくなり、ブランディングが機能しなくなってしまいます。
本章では、SNS運用の前提として必要な「ブランド設計のステップ」から、それをSNS施策へと落とし込んでいくための実践フローまでを、6つのステップに分けて解説します。
SNSでブランドの世界観を正しく伝えるには、見た目やトーンだけを整えるのでは不十分です。
重要なのは、「誰に、何を、どう伝えるか」というブランドの根幹=コンセプトをきちんと設計し、それをSNS上で表現することです。
ここでは、SNSブランディングの戦略設計から運用、改善までを5ステップに分けて解説します。特に初期段階であるSTEP1〜2では、マーケティングやブランド設計の理論に基づいた深堀が必要になります。
STEP1:消費者理解から始める(5C分析)
SNSブランディングの起点は、「自社がどう見られたいか」ではなく、「消費者が何を求め、どのように考えているか」を理解することです。
ここでは、マーケティング戦略の基礎である「5C分析」に基づき、ブランドを取り巻く状況を客観的に把握します。
Company(自社):自社の強み・独自性は何か?
Customer(顧客):消費者のニーズ、課題、価値観は?
Client(既存顧客):どんな層が既にブランドと接点を持っているか?
Competitor(競合):競合はどんな価値を訴求し、どこが弱点か?
Context(社会環境):法律、世論、文化など、時代背景との関係は?
さらに重要なのが、「凡人」と「狂人」に“憑依”するアプローチです。これは、理屈ではなく感情・本能レベルで消費者の思考を想像し、ブランドがどう刺さるかを考える方法です。
たとえば、「誰かに褒められたい」という欲求や、「人と違う自分でありたい」という承認欲求、あるいは「罪悪感なく甘えたい」といった矛盾した感情など──表層的なデモグラ情報の奥にある“衝動”まで想像することで、SNS上での表現にリアルな温度感を持たせることが可能になります。
STEP2:ブランド設計の仮説立案(ブランド・エクイティ・ピラミッド)
消費者への深い理解ができたら、次はそれをもとにブランドとしての“仮説”を構築します。このフェーズで活用できるのが「ブランド・エクイティ・ピラミッド」です。
ブランド・エクイティ・ピラミッド(構成要素)
Market(市場):自社が攻略すべきカテゴリー・文脈は?
Who(誰に)
ST(戦略ターゲット):ボリューム層として狙う層
CT(コアターゲット):ブランドの共感核になる理想顧客像
What(何を届けるか)
Benefit(価値):顧客にどんな“変化”や“感情”を与えるか
RTB(理由):その価値を信じてもらうための根拠・証拠
How(どのように届けるか)
POD(差別化ポイント):他社にはない、独自の強み
POP(同質化ポイント):最低限、業界的に満たすべき条件
BrandCharacter:ブランドを“人間”として捉えたときの性格・キャラ設定
このピラミッドを元に、ブランドの立ち位置や「言うべきこと/言わないこと」「表現すべきトーン」が明確になります。
SNSでは特に、**POD(差別化)とBrandCharacter(人格)**がユーザーの共感・拡散に大きく関わるため、ここを曖昧にせず言語化することが重要です。
このように、SNSブランディングの第一歩は「投稿案を考える」ではなく、「ブランドの内側を掘り下げ、設計すること」です。感性だけに頼らず、論理と共感の両面から設計されたコンセプトは、どんな投稿にも“芯”を持たせ、ユーザーの記憶に残るブランドを作る土台となります。
ここで初めて、SNS運用における「トーン」「ビジュアル」「コンテンツの方向性」が決められる状態になります。
STEP3:マーケティング・コンセプトの策定(STC設計)
ブランド設計の仮説を立てたら、次に取り組むべきは**“どのような文脈で伝えるか”を設計すること**です。単に価値を掲げるのではなく、「なぜ今、このブランドが必要なのか?」という“ストーリー”を消費者に届ける必要があります。
このフェーズで用いるのがSTC(SettingTheContext)という思考フレームです。STCとは、消費者がその価値を「自分に必要だ」と納得する文脈を設計する手法で、以下の3つの切り口があります。
①価値が高まるシーンを設定する
→例:「週末のちょっと贅沢な朝に」「特別な人との記念日に」など、価値が最大化される“状況”を想起させることで共感を引き出します。
②消費者インサイトを突く
→例:「可愛く見られたいけど、頑張ってる感は出したくない」など、消費者の葛藤や本音を言語化することで、リアリティのある訴求が可能になります。
③認識を変える“マインド・オープニング・インサイト”を活用する
→既存の価値観をくつがえすような、驚きや発見を与える表現です。たとえば、「忙しい=悪ではない」「ズボラこそ美しい」といった逆張りメッセージは、SNSでバズを生む起点にもなります。
加えて、エンタメ・ビューティー領域など感情を扱う領域では「ハート・オープニング・インサイト」が有効です。
これは、ユーザーの感情の奥にある“本音”や“ドロドロした感情”を突くアプローチで、情緒を大きく動かす投稿としてSNSと極めて相性が良い手法です。
このように、SNSでブランディングを行う際には、「なぜこの価値をいま、この文脈で伝えるのか?」というSTC的視点を挿入することで、投稿に物語と説得力が生まれます。
STEP4:定量・定性による検証
マーケティング・コンセプトをSNSに落とし込んだ後は、実際にその方向性が市場で機能しているかどうかを検証する必要があります。
ここで行うのが「量的調査(定量)+反応の分析(定性)」です。
定量評価
インプレッション数/エンゲージメント率/保存数/プロフィール遷移数などのSNS指標
定性評価
コメント・リプライ・引用・ストーリーズでの反応など、ユーザーの“声”や“文脈”を観察
このステップを軽視してしまうと、結果が出ない原因を「運用が悪い」と判断してしまい、根本のコンセプトがズレたまま投稿を繰り返すことになります。
SNSの反応は、消費者が“どう解釈したか”のフィードバックそのものです。数字だけでなく“ニュアンス”を捉える視点を持つことが大切です。
STEP5:マーケティングフレームワークへの落とし込み
ブランドの軸と、消費者の反応が一致していることが確認できたら、全体戦略へ落とし込みます。
ここでは、以下の4つの視点で設計すると、SNS以外の施策とも整合性の取れた戦略になります。これにより、ブランドの方向性と検証結果をもとに、一貫性のあるマーケティング設計へと統合していきます。
フレームワークとしては、以下のような「4階層」の整理が有効です。
✔戦況分析(AssessingTheLandscape)
市場トレンド、競合の動向、消費者行動の変化など、SNS上のデータも含めて現状を把握。
✔目的(Objective)
SNSを通じて、どのような状態を実現したいのか?(例:認知向上、想起率UP、エンゲージメント獲得)
✔戦略(Strategy)
どんな価値を軸に、誰に向けて何を発信するのか?(例:「忙しい女性に、手軽な贅沢時間を提案する」)
✔戦術(Tactic)
具体的に、どんな投稿コンテンツ・企画・媒体設計を行うか?(例:月曜は癒し投稿/水曜はライフスタイル提案)
ここまで設計されていれば、SNSだけでなく広告、イベント、販促、店舗接客なども一貫性ある世界観で統合される状態になります。
STEP6:ブランドと運用の“持続可能性”をつくる
最後に必要なのが、設計した世界観を運用で継続・強化する仕組みづくりです。SNSブランディングは、1回バズることではなく、時間をかけて「らしさ」を育てる行為です。
継続の鍵は以下の4点です。
ブランドトーン&マナーの運用ルール策定
運用ガイドラインの策定と更新(ブランドキャラクター、投稿例、NG表現など)
定期的なレビューとPDCA体制(月次での反応分析、方向性の見直し)
チームでの共有・共通言語化(外部パートナー含む関係者間での理解統一)
一貫性のあるSNSブランディングは、“ルールで縛る”のではなく、“芯を共有する”ことでこそ成立します。
このように、ブランドを“守る”体制=再現性ある世界観の運用設計を整えることで、SNSは戦略的なブランディングチャネルとして長期的に機能するようになります。
以上が、SNSブランディングを成功へ導くための6つのステップです。
「投稿の工夫」だけでなく、「思想の設計」からスタートすることで、SNSはブランド価値を深く届ける強力な武器になります。
SNSブランディングの効果をどう測るか? |

ブランドの世界観をSNSで発信し始めた後、「果たしてこの方向性は正しいのか?」「ユーザーに伝わっているのか?」と疑問を持つのは当然です。
しかし、SNSブランディングの効果は、キャンペーンのように短期的な成果で測れるものではなく、中長期的なブランド資産の蓄積として捉える必要があります。
この章では、SNSブランディングにおいて効果を評価する際の視点・指標・モニタリング方法について、実践的に解説します。
SNSブランディングは「測れない」のではなく「測るのが難しい」
SNSブランディングに取り組む中で、多くの担当者が抱えるのが「どうやって成果を評価すればいいのか?」という疑問です。
結論から言えば、ブランディングの効果は“測定不可能”ではありません。
ただし、厳密に測ろうとすれば、専門的なリサーチや高額な調査が必要になります。
たとえば、ブランド想起率やイメージの浸透度を定量的に把握するには、Webアンケート調査や街頭インタビュー、パネル調査などを実施する必要があります。しかし、これらは費用も手間も非常に大きく、すべての企業が定期的に実施できるわけではありません。
そのため実務においては、「SNS上の間接的な指標」をもとにブランドの浸透状況を捉え、継続的に改善していくことが現実的なアプローチとなります。
定量指標で見る:ブランドが“伝わっているか”の兆し
まずは、SNS上での反応を定量的に把握する視点が基本です。
ただし、ここでは「投稿の数字が多いか少ないか」ではなく、「ブランドイメージが伝わっているか」という観点で数値を解釈する必要があります。
たとえば、以下のような指標が参考になります。
プロフィール閲覧数:投稿を通じて、ユーザーがブランド自体に関心を持ったか
保存数・シェア数:単なる“いいね”よりも、ユーザーの行動意欲を測れる指標
ブランドハッシュタグの使用数:UGC(ユーザー生成コンテンツ)が増えているか
エンゲージメント率の推移:継続的な反応が得られているか
これらはあくまで“代替指標”ですが、ブランドの世界観が受け入れられ始めている兆しとして活用できます。
定性評価で見る:世界観が“どう解釈されているか”
SNSブランディングでは、数値だけでなくユーザーの言葉や行動の背景にある感情や印象を観察することが極めて重要です。
ブランドイメージの受け止められ方は、コメントや引用投稿、ストーリー反応などに現れます。
そのため、実務においてはあくまで間接的なKPI・ユーザー反応から、ブランディングの効果を推定するというのが現実的な対応策になります。
ユーザーの反応に“ブランドらしさ”が表れているか
コメント・保存・シェアの質と量が改善しているか
投稿の世界観が一貫して受け止められているか
たとえば、以下のような指標が参考になります。
「この世界観好き」「◯◯っぽくておしゃれ」などの共感コメント
投稿に対する引用・シェア文に含まれる形容詞や表現
他ユーザーがブランドをどう紹介しているか(口調・ニュアンス)
これらの“解釈のされ方”を定期的にモニタリングすることで、ブランドの人格や印象がユーザーの中でどう定着しているかを掴むヒントになります。
こうした「兆し」や「ニュアンス」の変化を読み取ることが、SNSブランディングの成果を捉えるうえで重要なのです。
なぜ「完璧に測れない」が前提なのか?
ブランディングは、コンバージョンやクリック率のように“即時性のある数字”で可視化されるものではありません。
そもそも、ブランドとは「人の心の中にある印象」であり、それは外からは完全には見えない性質を持っています。
厳密に測るには、以下のような本格的なリサーチが必要です。
ブランド想起調査(非誘導形式のWebアンケート)
タグラインやメッセージ認知度のテスト
イメージ評価の定量調査(心理学的なアプローチを含む)
しかし、これらは数百万円規模の費用が発生し、かつ定期的に行うには現実的なハードルがあります。
まとめ|SNSを軸に一貫したブランディングを |

SNSが生活に深く浸透し、情報収集の起点となった現代において、企業に求められるブランディングのあり方も大きく変化しています。
ユーザーが最初にブランドに触れるのがSNSであることも珍しくなく、そこで受け取る印象がブランドの評価を左右することも多々あります。
SNSでの情報発信が当たり前になった今、ブランドの世界観は投稿ひとつで伝わる時代です。しかし、その世界観に一貫性がなければ、ユーザーの記憶には残らず、ただの“投稿”として流れていってしまいます。
だからこそ、SNSブランディングは「何を投稿するか」ではなく、「誰に、何を、どんな文脈で届けるか」を明確にする設計が出発点です。本記事では、そのために必要なステップとして、消費者理解・ブランド設計・コンセプト立案から、SNS運用・評価の方法までを段階的に紹介してきました。
そして、SNSブランディングの効果は数字だけで測ることはできません。正確な調査には大きなコストがかかりますが、日々の“兆し”や“ニュアンス”を丁寧に読み取ることで、ブランドが伝わっているかを確かめることは可能です。
SNSは、ブランドとユーザーが日常的に出会う場所です。だからこそ、その設計と運用に戦略性があるかどうかが、数年後のブランドの姿を決定づけます。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。
ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するSNS施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。


















