司法書士が取り組むべきSNS運用とは?Instagram活用で集客と信頼を高める方法
- 株式会社ビーステップ

- 2025年11月1日
- 読了時間: 20分

 この記事の著者 | 山口巧己 地方×SNSマーケティングのスペシャリスト 大学在学中からSNSを独学し、父の車屋やインターンでのアウトドアブランドのSNS運用を行い、認知拡大・販売促進の向上、副次的に採用への貢献。この経験から紹介での依頼をいただき、大学4年生でフリーランスとして活動。 卒業後、WEBベンチャー企業で新規顧客開拓の営業へ従事する傍ら、フリーランス活動を継続。入社9ヶ月で退職し、独立。これまでの支援社数は50社を超える。 運用の"代行"ではなく、クライアントの経営戦略から逆算して結果へ繋げるためのSNSマーケティングが得意。 いい商品・サービス・会社を広めることが好きなSNSマーケオタク。 |
「紹介だけに頼った集客に限界を感じている」
「相談につながるSNS運用の方法がわからない」
「広告規制を意識すると何を発信してよいか不安」
──司法書士が抱える悩みは共通しています。
こうした課題を解決する手段が、戦略的なSNS運用です。
本記事では、司法書士にとってSNS運用がなぜ必要なのかを解説し、特にInstagramを活用した効果的な発信方法や成功事例、リスク管理のポイント、さらにWeb集客との掛け合わせ方までを詳しく紹介します。
記事を読むことで、信頼を築きながら新規相談を獲得するための実践的なステップが明確になります。
今すぐSNS運用に取り組み、地域から選ばれる司法書士事務所への第一歩を踏み出してください。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。
ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するSNS施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。
司法書士にとってSNS運用が重要な理由 |

司法書士が直面する課題の一つに「従来の集客手法だけでは限界がある」という現実があります。
折込チラシや紹介依存だけでは十分な新規顧客を確保できず、今やSNSを活用した運用が必要不可欠になっています。
この章では、SNS運用が司法書士にとって重要である理由を整理し、主に以下の3つの観点から解説します。
従来の集客手法の限界とデジタルシフト
SNSがもたらす「認知拡大」「信頼構築」「相談獲得」の効果
デジタル時代に対応する司法書士の姿勢
これらを踏まえることで、単なる流行ではなく「事務所経営に直結する投資」であると理解できるでしょう。
従来の集客手法の限界とデジタルシフト
司法書士にとってSNS運用が必要とされるのは、従来の集客方法に限界が見えているからです。
理由は明確で、紙媒体広告や口コミに頼るだけでは、情報を求める層に届かない現状があるからです。
例えば、法務局近隣に広告を出しても、今の相談者はまずスマホで検索やSNSを確認するのが一般的です。こうした行動変化に対応できなければ、新規顧客を獲得できる機会を失ってしまいます。
つまり、デジタルシフトに合わせてSNS運用を取り入れることが、現代の司法書士事務所には不可欠なのです。
SNSがもたらす「認知拡大」「信頼構築」「相談獲得」の効果
SNS運用を行うことで司法書士は大きなメリットを得られます。それは「認知拡大」「信頼構築」「相談獲得」の3つです。
理由として、SNSは潜在的な相談者に継続的に情報を届けられる点が強みだからです。
実際にInstagramでは、法律解説を図解で発信する司法書士が地域での知名度を高め、相談件数を増やした事例があります。
まとめると、SNSは単なる広告手段ではなく、信頼を積み重ねる場であり、その結果として集客効果を発揮するのです。
デジタル時代に対応する司法書士の姿勢
司法書士がSNS運用に取り組む姿勢は、単なる宣伝活動にとどまりません。
なぜなら、相談者が求めているのは「専門性」だけでなく「相談しやすさ」「親近感」といった人間的要素だからです。
例えば、事務所の日常や取り組みを発信している司法書士は、地域住民から「話しかけやすい専門家」として評価されています。
まとめると、デジタル時代の司法書士には、専門知識を発信しながら人柄も伝えるバランス感覚が求められるのです。
SNSの利用実態をより詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
司法書士が取り組むべきSNS運用の全体像 |

SNS運用は単なる情報発信ではなく、計画性を持ったマーケティング活動として設計する必要があります。
司法書士が効率的に活用するためには、運用の基本概念を理解したうえで、各SNSの特徴を把握し、自身の業務との相性を考えることが大切です。
ここでは、次の3つの観点から解説します。
SNS運用と単なる投稿の違い
主要SNSの特徴比較(Instagram・X・YouTube・Facebook)
司法書士業務とSNS媒体の相性
これらを整理することで、どのようなSNS運用が事務所の成長につながるのかを把握できるようになります。
SNS運用と単なる投稿の違い
SNS運用と単なる投稿は似ているようで大きく異なります。
運用とは、目的を設定し、ターゲットを明確にし、投稿内容や頻度を計画的に管理することです。
理由として、偶発的な投稿では一貫性がなく、ブランドとしての信頼を構築できないからです。
例えば、司法書士が不定期に業務の写真を載せるだけでは「情報発信」に過ぎません。
しかし、相談者の悩みに沿ったテーマを計画的に発信すれば、それは「SNS運用」となり、問い合わせにつながる導線を生み出せます。
まとめると、SNS運用は戦略的に集客やブランディングを行う仕組みそのものなのです。
主要SNSの特徴比較(Instagram・X・YouTube・Facebook)
SNSを運用する際には、それぞれの媒体の特徴を理解することが重要です。
なぜなら、同じ内容を一律に発信しても、利用者層や目的が異なるため効果が分散してしまうからです。
実際に、Instagramはビジュアル重視で地域密着に強く、X(旧Twitter)は速報性が高く権威性を高めやすいという特性があります。YouTubeは長尺で深い解説ができるため専門性を伝えるのに適しており、Facebookは幅広い年齢層に訴求できます。
まとめると、各SNSの特徴を比較し、司法書士が発信すべき内容を媒体ごとに最適化することが効果的な運用の鍵となります。
司法書士業務とSNS媒体の相性
司法書士がSNS運用を考える際は、自身の業務との相性を重視すべきです。
理由として、司法書士業務には専門性と地域性の両方が関わり、どのSNSを活用するかで成果が大きく変わるからです。
例えば、相続や登記など地域住民を対象とする案件はInstagramやFacebookとの相性が良く、専門性を深く解説して差別化を図りたい場合にはYouTubeが有効です。
また、Xでは同業者や法律関係者との横のつながりを広げることができます。
つまり、司法書士は自分の業務内容やターゲットに合わせて媒体を選び、相性の良いSNSで運用を強化することが成果への近道です。
SNSごとの役割をより俯瞰的に理解したい方は、SNSマーケティング全体をまとめたこちらの記事もおすすめです。
Instagram運用が司法書士に特に有効な理由 |

数あるSNSの中でも、司法書士にとって特に効果を発揮しやすいのがInstagramです。
利用者層の広がりや情報収集ツールとしての地位向上により、専門家が発信する場として注目されています。
この章では、Instagram運用が司法書士に有効である理由を3つの観点から解説します。
視覚的な情報発信で専門性をわかりやすく伝える
人柄や事務所の雰囲気を見せることで相談ハードルを下げる
地域密着型の発信が相談獲得に直結する
これらを理解することで、Instagramの強みを司法書士業務に最大限活かせるようになります。
視覚的な情報発信で専門性をわかりやすく伝える
Instagramが司法書士に有効な理由のひとつは、専門知識を視覚的に伝えられることです。
なぜなら、相続や登記といった難しいテーマも、図解やインフォグラフィックを用いることで理解が進みやすくなるからです。
例えば、ある司法書士は「相続手続きの流れ」をフローチャート形式で投稿し、フォロワーから「分かりやすい」と好評を得ています。このように、文字だけでは伝わりにくい専門情報をビジュアルで補足できる点は大きな強みです。
つまり、Instagramは複雑な業務内容をシンプルに伝える場として非常に適しています。
人柄や事務所の雰囲気を見せることで相談ハードルを下げる
司法書士に相談する際、多くの人は「専門家に話しかけるのは敷居が高い」と感じています。Instagramでは、この心理的ハードルを下げることが可能です。
理由は、業務の合間の様子やスタッフの日常を投稿することで、相談者に親近感を持ってもらえるからです。
実際に、事務所の雰囲気やスタッフ紹介を投稿している司法書士は、地域住民から「話しやすい印象を持った」と評価され、問い合わせにつながったケースがあります。
結論として、Instagramは人柄を伝えることで信頼を築き、相談を促進する効果を発揮します。
地域密着型の発信が相談獲得に直結する
司法書士の業務は地域性が強く、地元の相談者からの依頼が中心です。
そのため、Instagramで地域に関連する発信を行うことは、相談獲得に直結します。
なぜなら、地域のイベントや法務関連の情報を共有することで、「身近に頼れる専門家」として認知されやすくなるからです。
例えば、地域の無料相談会や登記関連の最新情報を発信している司法書士は、地元での認知度が高まり、相談件数の増加につながっています。
要するに、Instagramは地域密着型の発信に適した媒体であり、司法書士の集客戦略において欠かせない存在なのです。
投稿をより多くのユーザーに届ける『拡散』の仕組みを理解しておくと、Instagram運用の効果が高まります。
さらに、一貫したブランドイメージの構築には、SNSブランディングの考え方も欠かせません。
以下の関連記事も合わせてお読みください。
SNS運用を成功させる実践ステップ |
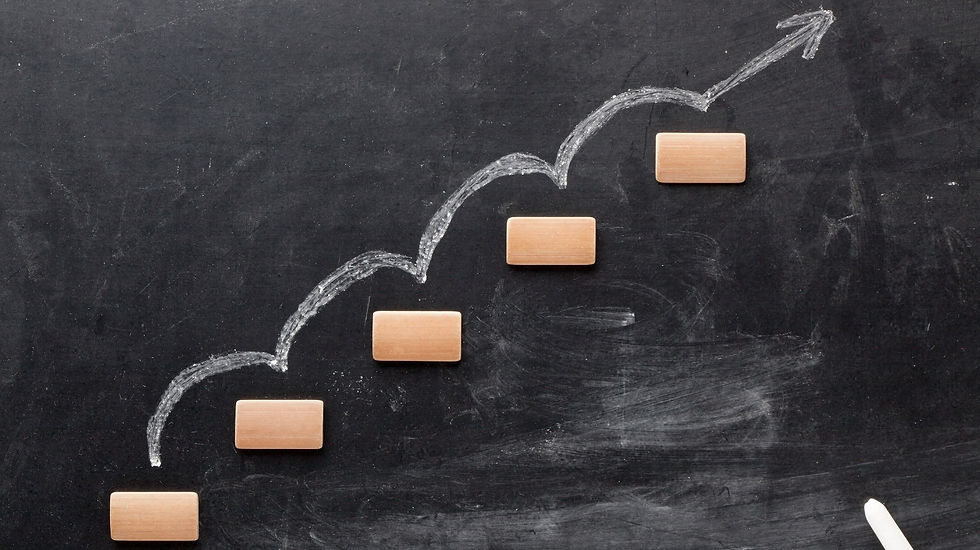
司法書士がSNSを効果的に活用するには、単に投稿を続けるだけでは不十分です。
戦略的にSNS運用を設計し、継続できる仕組みを整える必要があります。
この章では、SNS運用を成功に導くための4つのステップを紹介します。
ビジネスアカウント設定とプロフィール最適化
発信テーマの選定(業務解説・日常・地域活動)
投稿フォーマットの工夫(図解・ショート動画・ストーリーズ)
継続的な発信とコミュニケーション設計
これらを意識することで、相談者から「信頼できる専門家」と認識されるSNS運用を実現できます。
ビジネスアカウント設定とプロフィール最適化
SNS運用を始める際に最初に取り組むべきは、ビジネスアカウントの設定とプロフィールの整備です。
なぜなら、プロフィールは「第一印象」として事務所の信頼性を左右するからです。
例えば、プロフィールに業務内容や所在地、相談できるテーマを明確に記載する司法書士は、ユーザーから安心感を持たれやすくなります。
逆に情報が曖昧だと信頼性を損ない、問い合わせにつながりません。
結論として、正確かつ分かりやすいプロフィール設計はSNS運用の基盤となります。
発信テーマの選定(業務解説・日常・地域活動)
次に重要なのは、どんなテーマで発信するかを定めることです。
理由は、投稿内容が一貫していないとフォロワーが何を期待すればよいのか分からず、継続的な関心を得られないからです。
例えば、業務内容の分かりやすい解説に加えて、日常風景や地域活動を発信する事務所は、専門性と親近感を同時に伝えることができます。
まとめると、司法書士は「専門知識+人柄+地域性」をバランス良く発信することで、相談につながる信頼を育てられるのです。
投稿フォーマットの工夫(図解・ショート動画・ストーリーズ)
SNS運用では、発信内容だけでなく形式の工夫も成果に直結します。
理由は、ユーザーは短時間で情報を理解したいと考えており、フォーマット次第で理解度や印象が変わるからです。
例えば、相続手続きの流れを図解にまとめた投稿や、登記に関するQ&Aをショート動画で発信することで、難しいテーマでも関心を持ってもらいやすくなります。
また、ストーリーズを活用すればリアルタイム感を演出できます。
要するに、フォーマットの工夫は司法書士の専門性を効果的に届ける手段なのです。
継続的な発信とコミュニケーション設計
最後に重要なのは、継続的に発信しフォロワーと関係を築く仕組みを設けることです。
理由として、SNSは一度の投稿で成果が出るものではなく、信頼を積み重ねるプロセスが必要だからです。
実際に、週数回の定期的な投稿を行い、コメントやDMに丁寧に返信している司法書士は、フォロワーからの相談率が高まっています。
まとめると、計画的な更新と双方向のコミュニケーションを重視することが、SNS運用の成功に不可欠なのです。
司法書士が活用できるSNS広告の種類と効果 |

SNS運用を軌道に乗せるためには、自然投稿だけでなく広告を戦略的に活用することが有効です。
広告は潜在層へのアプローチを可能にし、短期間で認知を拡大できます。
この章では司法書士に特に適した主要SNS広告の特徴と効果を整理します。
Instagram広告
X広告
YouTube広告
Facebook広告
TikTok広告
それぞれの特性を理解することで、予算や目的に応じた効果的な広告活用が可能となります。
Instagram広告
司法書士にとってInstagram広告は、地域に根ざした相談者へのアプローチに適しています。なぜなら、Instagramは位置情報や属性を絞り込んだ配信が可能で、視覚的な投稿との親和性が高いからです。
例えば、相続相談のセミナー案内を地域ターゲティングで配信した事務所では、短期間で参加者を獲得する成果が出ています。まとめると、Instagram広告は地域密着の司法書士にとって即効性のある集客施策です。
X広告
X(旧Twitter)の広告は、速報性の高い情報発信を支援します。理由は、時事的な法律改正や制度変更といった情報を即座に発信できるため、専門家としての立ち位置を強化できるからです。
例えば、法改正に関するツイートを広告で拡散した司法書士は、業界関係者からの認知が広がり、メディア取材の依頼にもつながりました。結論として、X広告は権威性の確立を狙う司法書士に効果的です。
YouTube広告
YouTube広告は、司法書士の専門性を深く伝えたい場合に有効です。なぜなら、長尺の動画を通して具体的な手続きや成功事例を解説でき、視聴者に専門家としての信頼を与えられるからです。
実際に、登記や相続に関する解説動画を広告配信した司法書士は、事務所名の検索数が増加し、長期的なブランディング効果を得ています。つまり、YouTube広告は信頼を積み重ねる中長期戦略に向いています。
Facebook広告
Facebook広告は、幅広い年齢層にリーチできる点が強みです。理由として、中高年層の利用者が多いため、相続や遺言といった司法書士の主要業務との親和性が高いからです。
例えば、遺言書作成サポートを紹介する広告を配信した場合、40代以上の層からの問い合わせが増えた事例があります。要するに、Facebook広告は相談件数を安定的に確保するために有効な手段なのです。
TikTok広告
TikTok広告は司法書士にとって新しい可能性を持つ媒体です。なぜなら、若年層が中心のプラットフォームであり、早期にブランド認知を形成できるからです。
例えば、相続や不動産登記を「知っておくべき基礎知識」として短い動画で発信すれば、学生や若い社会人の間で認知度が高まります。まとめると、TikTok広告は今すぐの相談につながらなくても、将来の相談候補を育成する役割を果たします。
主要SNS広告の特徴や運用のコツをさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事も合わせてお読みください。
成功事例から学ぶ司法書士のSNS運用 |

SNS運用は、理論を理解するだけでは成果につながりません。
実際にどのように活用されているのか、具体的な成功事例を見ることで、自分の事務所での実践イメージが明確になります。司法書士の中には、Instagram・YouTube・Xを横断的に活用し、それぞれの特性を活かしながら成果を挙げている方々がいます。
本章では、特に参考になる3つのアカウントを取り上げ、その運用の工夫と効果を解説します。
加陽麻里布司法書士

加陽氏は、SNSごとに役割を明確に分けた運用を行っています。Instagramでは図解やスライド形式を活用し、相続や登記の専門知識を視覚的に分かりやすく伝えています。YouTubeでは長尺の解説動画を通して詳細な知識を提供し、専門家としての信頼を確立。Xでは時事ニュースや法改正の話題をタイムリーに発信し、速報性と権威性を両立しています。こうした横断的な活用は、幅広い層に効果的にリーチできる好例です。
植田麻友司法書士

植田氏は、専門性と親しみやすさを兼ね備えた発信でフォロワーの支持を集めています。Instagramでは「相談しやすい司法書士」という印象を与える日常投稿と、業務に役立つ情報を組み合わせています。YouTubeでは具体的な事例解説を通して信頼を高め、Xでは軽快な発信でフォロワーとの距離を縮めています。媒体ごとにトーンを変える工夫が秀逸で、個人ブランディングの成功事例といえます。
グリーン司法書士法人

グリーン司法書士法人は、法人としてのブランディングを重視した発信が特徴です。Instagramでは相続や不動産に関する情報を地域住民に向けて発信し、地元に密着した専門家というポジションを確立しています。YouTubeでは相続手続きを中心に専門性を深く掘り下げ、信頼性を高めています。さらにXでは業界ニュースや法人活動を共有することで、広域的な認知と権威付けを行っています。個人アカウントと法人アカウントを連動させる姿勢も参考になります。
これらの事例に共通しているのは「SNSを横断して役割を使い分けていること」です。Instagramで視覚的な認知を拡大し、YouTubeで専門性を深掘りし、Xでタイムリーな情報を補完するという流れは、司法書士における理想的なSNS運用モデルといえるでしょう。
SNS運用における注意点とリスク管理 |

司法書士がSNSを運用する際には、メリットだけでなくリスクへの対応も欠かせません。専門職である以上、発信内容には法的制約や社会的責任が伴います。この章では、SNS運用において特に注意すべき点を整理し、安心して継続できるためのポイントを解説します。
司法書士法の広告規制と表現の境界線
守秘義務と個人情報保護への配慮
炎上や同業者からの批判対応
運用体制と継続発信の仕組みづくり
これらを理解しておくことで、リスクを未然に防ぎ、長期的に信頼される発信を行うことが可能となります。
司法書士法の広告規制と表現の境界線
司法書士がSNSを運用する際、まず意識すべきは司法書士法に基づく広告規制です。理由は、誇大表現や比較広告が禁止されており、違反すると懲戒や指導の対象となる可能性があるからです。
例えば、「必ず成功する」「地域で一番安い」といった表現は不適切で、信頼性を損なう恐れがあります。実際には「実績に基づく事例紹介」や「相談可能な業務内容の明示」にとどめることが求められます。結論として、SNSでも法律広告と同様の慎重さが必要なのです。
守秘義務と個人情報保護への配慮
SNS発信で特に注意すべきもう一つの点は、相談者のプライバシーです。理由は、司法書士には厳格な守秘義務が課されており、無意識の投稿でも個人が特定される恐れがあるからです。
例えば、相続相談のエピソードを紹介する際に、地域や家族構成などを具体的に記すと個人情報が漏洩するリスクがあります。そのため、実際の事例を紹介する場合は必ず匿名化や一般化を行う必要があります。つまり、守秘義務を徹底することで初めて信頼できるSNS運用が実現します。
炎上や同業者からの批判対応
SNSは拡散性が高い分、炎上や批判のリスクも伴います。司法書士は専門家としての責任を負う立場にあるため、誤解を招く発信や過激な表現は避けるべきです。
例えば、同業者から「不正確な表現」と指摘されるケースもあります。このような場合、感情的に反論するのではなく、事実に基づいて冷静に訂正や説明を行うことが重要です。まとめると、批判対応を適切に行える体制を整えることが、SNS運用を長期的に成功させるカギとなります。
運用体制と継続発信の仕組みづくり
SNS運用の失敗要因の多くは「続かないこと」にあります。理由は、日常業務が忙しい中で片手間に運用してしまうと更新が途絶え、効果が出ないまま終わってしまうからです。
例えば、投稿カレンダーを作成し、事務所内で担当者を決めて役割分担を行えば、継続性を担保できます。また、外部のSNS運用代行を活用するのも一つの手段です。結論として、継続的な発信体制を整えることがリスク管理にも直結します。
SNSとWeb集客を掛け合わせる戦略 |

SNS運用だけでも一定の効果は見込めますが、司法書士事務所の集客を最大化するにはWeb施策との連携が欠かせません。
SNSは入口を広げる役割を果たし、Webサイトや検索対策は受け皿として機能します。
この章では、SNSとWeb集客を組み合わせるための主要なポイントを紹介します。
ホームページ・SEOとの連携
MEO対策で地域検索に対応
ポータルサイト登録との組み合わせで接点を最大化
これらを実行することで、SNSで興味を持ったユーザーを確実に問い合わせや相談につなげることが可能となります。
ホームページ・SEOとの連携
SNS運用とホームページは相互補完の関係にあります。なぜなら、SNSで興味を持ったユーザーは、最終的に事務所の信頼性を確認するためホームページを訪れるからです。
例えば、Instagramの投稿から「詳しくはこちら」と公式サイトに誘導し、SEOで上位表示されたページで手続き方法を解説していれば、自然な流れで相談予約につながります。結論として、SNSは集客の入口、ホームページとSEOは成約の出口として設計することが重要です。
MEO対策で地域検索に対応
司法書士の業務は地域密着型であるため、Googleマップでの検索結果に表示されることが大きな影響を持ちます。理由は、ユーザーが「司法書士+地域名」で検索した際に、上位に表示される事務所が優先的に選ばれるからです。
例えば、SNSで地域活動の様子を発信しつつ、Googleビジネスプロフィールを整備している司法書士は、検索結果からの問い合わせが増加しています。まとめると、SNSとMEOを掛け合わせることで、地域での存在感を強固にできるのです。
ポータルサイト登録との組み合わせで接点を最大化
司法書士の集客では、SNSやSEOだけでなくポータルサイトへの登録も有効です。理由は、相談者の中には「専門家検索サイト」から情報収集を始める人も多いからです。
例えば、司法書士会の公式ポータルや法律系の専門サイトに事務所情報を掲載している場合、SNSから流入したユーザーが「この先生はポータルにも掲載されている」と確認でき、信頼が一層高まります。要するに、SNSとポータルサイトを組み合わせることで、多角的な接点をつくり出せるのです。
まとめ |

司法書士にとってSNS運用は、単なる広報活動ではなく、事務所の成長に直結する経営戦略です。SNSを通じて新規相談者との接点をつくり、継続的な発信で信頼を積み重ね、最終的には「選ばれる専門家」としてのブランドを築くことが可能になります。
特にInstagramは、専門性を分かりやすく伝え、人柄や事務所の雰囲気を見せるのに適しており、地域密着型の相談獲得に直結します。また、XやYouTubeなど複数のSNSを組み合わせることで、幅広い層にアプローチできる点も強みです。
デジタル時代において、SNSでの発信は司法書士に欠かせない信頼構築の手段です。今すぐにSNS運用を始めることが、将来の相談獲得や事務所経営の安定につながります。もし自力での運用に不安があれば、専門家の支援を活用しながら第一歩を踏み出すことをおすすめします。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。
ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するInstagram施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。





















