企業がYouTubeを活用するメリットとは?成功事例・注意点・始め方を徹底解説
- 2025年9月5日
- 読了時間: 24分

 この記事の著者 | 山口巧己 地方×SNSマーケティングのスペシャリスト 大学在学中からSNSを独学し、父の車屋やインターンでのアウトドアブランドのSNS運用を行い、認知拡大・販売促進の向上、副次的に採用への貢献。この経験から紹介での依頼をいただき、大学4年生でフリーランスとして活動。 卒業後、WEBベンチャー企業で新規顧客開拓の営業へ従事する傍ら、フリーランス活動を継続。入社9ヶ月で退職し、独立。これまでの支援社数は50社を超える。 運用の"代行"ではなく、クライアントの経営戦略から逆算して結果へ繋げるためのSNSマーケティングが得意。 いい商品・サービス・会社を広めることが好きなSNSマーケオタク。 |
企業の情報発信や集客手段として、YouTubeの活用はますます重要性を高めています。
新規顧客の獲得からブランド強化、採用活動まで、動画を使った取り組みには多くのメリットがあります。
しかし同時に、コストや炎上リスクなど注意すべき点も存在します。
本記事では、企業がYouTubeを活用するメリットとデメリット、実際の成功事例、導入ステップから失敗回避策までを整理し、成果につながるYouTube活用の第一歩を分かりやすく解説します。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。
ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するYouTube施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。
目次
企業がYouTubeを活用するべき理由 |

これまで企業が直面する課題を整理しましたが、その解決策の一つとして注目されているのがYouTubeの活用です。
企業がYouTubeを利用すべき理由は主に2つあります。
動画マーケティング市場の拡大とYouTubeの成長性
企業にとっての重要な役割
これらを理解することで、YouTube活用が単なるトレンドではなく、企業戦略として不可欠であることが分かります。
動画マーケティング市場の拡大とYouTubeの位置づけ
YouTubeを活用すべき最大の理由は、動画マーケティング市場そのものが拡大を続けているからです。
理由としては、消費者が視覚と聴覚を同時に刺激されるコンテンツに強く引きつけられ、購買行動に直結しやすい点が挙げられます。
例えば、国内でも動画広告市場は毎年成長しており、企業が従来型の広告だけに頼るのは非効率になっています。
つまり、YouTubeはその中心的な媒体として、企業が顧客とつながるうえで避けて通れない存在となっているのです。
企業にとってYouTubeが重要視される背景
企業にとってYouTubeが重要なのは、単なる認知拡大だけでなく「顧客理解の深化」に直結するためです。
理由は、動画を通じて自社の理念や商品価値をわかりやすく伝えられるため、文字や静止画では伝わりにくい魅力を届けられるからです。
例えば、採用活動で社内の雰囲気を動画で伝えると、求職者の安心感や共感を得やすくなります。
まとめると、YouTubeは企業が顧客や人材に対して信頼を積み上げる強力な手段であり、今後さらに重視される領域だといえます。
企業がYouTubeを活用するメリット |

YouTube活用には数多くの利点がありますが、特に企業にとって成果に直結するのは次の5つです。
新規顧客獲得につながる
ブランド認知度と信頼性の向上
商品・サービス理解促進と購買意欲向上
長期的な資産としての動画活用
採用活動や社内ブランディングへの応用
これらのメリットを正しく把握することで、企業はYouTubeを短期的な施策ではなく、中長期的な資産形成の手段として捉えることができます。
新規顧客獲得につながる
YouTubeは新規顧客との接点をつくる最適な場です。
理由は、Google検索と連動しているため、自社を知らない潜在層にも動画が表示されやすいからです。
たとえば製品の使い方や業界の基礎知識を解説する動画は、調べ物をしているユーザーに刺さりやすく、購買意欲が芽生えるきっかけになります。
実際に検索から動画を経由してWebサイトへ誘導できるケースは多く、見込み顧客を自然に集客できるチャネルとして価値があります。
ブランド認知度・信頼性の向上
YouTubeは企業のブランドを広め、信頼を築くメディアとして有効です。
なぜなら、動画は文字や画像よりも「人の姿」「声」「雰囲気」を伝えやすく、親近感を生み出すからです。
たとえば社員や経営者が登場する動画は「顔の見える情報発信」となり、視聴者に安心感を与えます。さらに専門的なノウハウを発信すれば、業界内での権威性も高まります。
結果として、ブランドの知名度と信頼性を同時に向上させることが可能です。
商品・サービスの理解促進と購買意欲の向上
動画は商品やサービスの理解を深める最も直感的な手段です。
理由は、映像と音声で「使い方」や「効果」を具体的に見せられるためです。
たとえば、デモンストレーションや導入事例を紹介すれば、利用シーンをイメージできるようになり、購買意欲が高まります。調査によっても「購入前に商品動画を視聴したユーザーは、そうでない人に比べ購買率が高い」ことが示されています。
つまり、理解と納得を提供することで購買行動を後押しするのがYouTubeの強みです。
長期的な資産としての動画活用(営業・教育ツール化)
YouTubeにアップした動画は長期的に価値を生み続ける資産になります。SNS投稿のように流れて消えてしまうことがなく、検索や関連動画経由で繰り返し視聴されるからです。
たとえばFAQ動画や商品マニュアル動画は、営業担当者が毎回説明する手間を省き、顧客自身が理解を深めることで商談の質を高められます。また、社員研修やマニュアル共有の場面でも再利用でき、教育ツールとしても効率的です。
さらに、一度制作した動画は広告として活用したり、Webサイトや他SNSに埋め込むことで多用途に展開可能です。
つまり、一度の投資で長期にわたり営業支援・顧客教育・社内教育の3つを支えるのがYouTube動画の大きな強みです。
採用活動や社内ブランディングにも活用できる
YouTubeは採用と組織強化のツールとしても効果を発揮します。
理由は、社内の雰囲気や社員の声を動画でリアルに伝えられるからです。
たとえば社員インタビューやオフィス紹介の動画は、応募者の不安を解消し、入社前の期待感を高めます。また既存社員にとっても「自分の会社がどう発信されているか」を共有することで誇りや一体感が生まれます。
つまり、外部への採用広報と内部のブランディング強化を同時に実現できるのです。
企業がYouTubeを活用するデメリット・注意点 |

大きな可能性を持つYouTubeですが、デメリットや注意点を理解しておかないと逆効果になる場合もあります。
主に次の4点が課題として挙げられます。
制作や運営にコストとリソースがかかる
成果が出るまで時間を要する
炎上や著作権リスクが存在する
継続的な運営体制が求められる
これらを認識して事前に対策を講じることが、安心してYouTubeを導入する第一歩になります。
制作・運営にコストとリソースがかかる
YouTubeは無料で始められる一方で、本格的に成果を出すには相応のコストが必要です。
企画、撮影、編集など複数の工程があり、すべてを内製すれば人件費や工数が膨らみます。
外注を利用すれば1本あたり数十万円規模の費用が発生することも珍しくありません。
また、社内に専門人材がいない場合は教育コストもかかります。つまり、継続的にリソースを投下できる体制がなければ途中で頓挫する可能性が高いのです。
成果が出るまで時間が必要
YouTubeは短期間で成果を出す施策には不向きです。
理由は、アルゴリズムがチャンネルを評価するまでに一定の投稿数と時間が必要だからです。
週1回投稿を続けても、効果が出始めるのは半年以降というケースも少なくありません。
短期的に売上を求める企業が「すぐに結果が出ない」と途中で諦めるのはよくある失敗例です。
YouTubeは中長期で資産を形成するメディアであると理解し、腰を据えて取り組むことが大切です。
炎上リスクや著作権への配慮が必要
企業がYouTubeを運営する際には、炎上リスクや著作権侵害への注意が欠かせません。
なぜなら、動画はSNSで拡散されやすく、少しの不適切表現が大きな批判につながる可能性があるからです。
例えば、差別的と捉えられる発言や過激な演出は一気にブランド価値を下げかねません。
また、BGMや画像を無断で使用すれば、著作権違反として動画削除や収益化停止の処分を受けることもあります。
企業チャンネルは信頼を前提に運営されるため、事前に法的チェック体制や炎上対応マニュアルを整えることが必須です。
さらに、コメント欄の管理体制を構築し、ネガティブな反応に冷静かつ迅速に対応できる仕組みを持つことで、リスクを最小限に抑えることができます。
継続的な運営体制の構築が不可欠
YouTubeは継続して初めて成果が積み上がる媒体であり、数本投稿して放置するだけでは効果を得られません。むしろ「更新されていないチャンネル」として企業の信頼を損なう恐れさえあります。
実際、多くの企業が最初の数か月で投稿が止まり、ブランドイメージに悪影響を及ぼす事例も見られます。
これを防ぐには、最初から無理のない投稿頻度を設定し、撮影・編集・分析を分担できる体制をつくることが重要です。
また、社内だけでリソースが足りない場合は外注や代行サービスを併用するのも有効です。
つまり、「続ける仕組み」を先に整えることが、成果を出す前提条件なのです。長期的に運営できる体制を築くことが、YouTube活用を資産化へと導きます。
YouTube活用が向かない企業・ケース |

YouTubeは多くの企業にとって有効な手段ですが、すべての企業に適しているわけではありません。
無理に導入しても効果が得られず、リソースを浪費してしまう場合があります。
特に成果が出にくいのは以下のケースです。
即効性を求めすぎている場合
リソースが確保できない場合
ターゲットがYouTubeを利用していない場合
これらの条件に当てはまる企業は、他の手法を優先した方が効率的な可能性があります。
即効性だけを求めているケース
YouTubeは短期間で成果を出す施策には向きません。
なぜなら、アルゴリズムがチャンネルを評価するには一定の投稿数と継続期間が必要だからです。
実際に週1本の更新を半年以上続けて初めて効果が見え始めることも少なくありません。
したがって「1〜2本の動画で集客したい」「1か月以内に売上を上げたい」と考える企業は、期待外れに終わる可能性が高いです。
短期施策が必要なら、リスティング広告やSNS広告など即効性のある手法を選んだ方が現実的でしょう。
リソースが確保できないケース
YouTube運営は企画・撮影・編集・分析など複数の工程があるため、片手間で運営するのは困難です。担当者が兼任で運営すると更新が滞り、むしろ「情報発信を継続できない企業」というマイナスの印象を与えるリスクもあります。
継続的に投稿するには、少なくとも1〜2名が安定して時間を割ける体制、または外部パートナーの活用が必要です。
こうしたリソースを確保できない企業は、YouTubeを始めるよりも既存チャネルの改善に注力する方が投資対効果は高いといえます。
ターゲットがYouTubeを利用していない業界
YouTubeは幅広い層に利用されていますが、必ずしもすべての業界や顧客層に適しているわけではありません。
例えば高齢者が主要顧客の一部の業界では、テレビや新聞、チラシなどオフライン媒体の方が効果的な場合があります。
また、BtoBの中でも購買プロセスが閉じた業界では、展示会や業界紙の方が成約に直結するケースもあります。
重要なのは「自社のターゲットはどこで情報を得ているのか」を見極めることです。
ターゲットがYouTubeを利用していない場合は、無理に参入するよりも適切な媒体に集中する方が効率的です。
ちなみにですが、あなたの会社の競合はYouTubeを活用していますか?
もし活用しているのであれば早く取り入れないと先行者利益を取られますし、まだ活用していないのであれば競合を出し抜くチャンスが眠っています。
でも自社でやるのは難しいと感じるけど、
「YouTube運用を外部に依頼しようと思ってもどこがいいのかわからない・・・。」
このように思うことはありませんか?
そんな方は、ぜひ以下の関連記事を参考にしてみてください。
企業YouTubeの成功事例 |

ここまでで、YouTubeが企業にもたらすメリットや注意点を整理しました。
では実際に、どのような企業が成果を上げているのでしょうか。
理論だけでなく、実際の成功事例から学ぶことは大きな意味があります。
ここでは、異なる業界・規模の5つの事例を紹介します。
フランチャイズチャンネル
年収チャンネル
脱・税理士スガワラくん
ウェルネストホーム九州
エンジニアファースト
それぞれの特徴と成果を知ることで、自社に応用できるヒントを得られるはずです。
フランチャイズチャンネル
フランチャイズチャンネルの登録者数は約20万人、平均再生数は1,000〜5,000回と決して多くはありませんが、再生数よりも「どの層に刺さるか」を重視した運営が特徴です。ニッチな層に深く刺さる企画を続けることで、結果的に年商10億円を達成しました。量ではなく質を重視したYouTube活用が、事業成長に直結している好例といえます。
年収チャンネル
年収チャンネルの登録者数は29万人、各企業の収入や働き方といったテーマを扱い、就活生を中心に人気を集めていましたが、今では社会人や経営者層にまで広がっています。特筆すべきは2023年に開催されたフリーランスサミット。広告費を一切かけず、YouTube動画での告知だけで4,500人の集客に成功しました。知名度拡大と集客力を両立させた事例です。
脱・税理士スガワラくん
脱・税理士スガワラくんの登録者数は124万人、お金に関する有益な情報や、ギリギリな裏ワザを分かりやすく解説することで爆発的な支持を集めています。専門性の高さが信頼を生み、さらに人柄やストーリー性を交えた発信でファンを固定化。結果として、専門知識と個人の魅力を掛け合わせることでブランド力を確立した代表的な事例といえます。
ウェルネストホーム九州
ウェルネストホーム九州の登録者数は3,200人と規模は大きくありませんが、高単価商材である超高性能住宅の価値をしっかり伝える場として機能しています。現場の紹介や施主インタビューを通じて信頼感を醸成し、来場や商談につなげているのが特徴です。登録者数の大小にかかわらず、質の高いリードを獲得できる点を示す好例といえるでしょう。
エンジニアファースト
エンジニアファーストは登録者数は約2.3万人、フリーランスエンジニアの採用を目的に運営されており、動画公開からのLINE誘導を通じて継続的な接点を作り出しています。その結果、採用ゼロから87名の採用を実現しました。動画コンテンツではプログラミング言語の将来性や収入といった実務的テーマを取り上げ、求職者の理解を深めつつ応募意欲を高めています。採用活動とYouTubeの親和性を示す好事例です。
企業がYouTubeを導入するステップ |
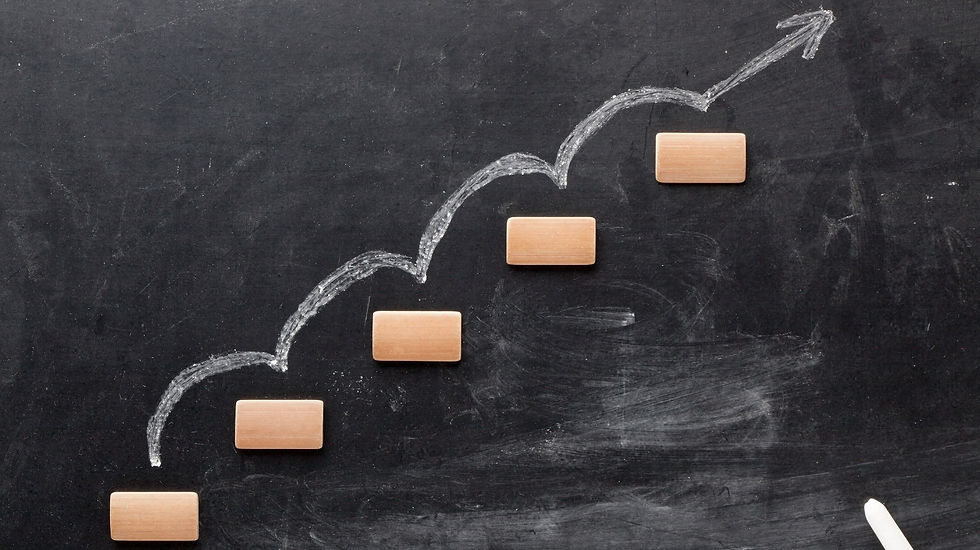
YouTubeを企業で活用するにあたっては、思いつきで動画を投稿するのではなく、あらかじめ計画的なステップを踏むことが成功の条件となります。
ここでは、導入から運用までの流れを5つの段階に分けて解説します。
目的とターゲットを設定する
コンセプトを設計する
コンテンツ企画と投稿スケジュールを決める
制作体制を整える
データ分析と改善を繰り返す
この流れを押さえておくことで、無駄なく戦略的にYouTubeを始められます。
チャンネルの目的・ターゲットを設定する
YouTubeを企業で始める際に最初に行うべきは、チャンネルの「目的」と「ターゲット」を明確化することです。
目的が新規顧客の獲得なのか、既存顧客の教育なのか、あるいは採用強化なのかによって、発信内容も大きく変わります。同時に、誰に見てもらいたいのかを具体化することが重要です。
例えば20代社会人を狙う場合と経営者層を狙う場合では、選ぶテーマや語り口調が大きく異なります。目的とターゲットが曖昧なままでは成果が出にくく、動画の方向性もぶれてしまうため、ここで徹底的に定義することが成功への第一歩となります。
コンセプトを設計する
目的とターゲットを決めたら、次に必要なのはチャンネル全体のコンセプト設計です。
コンセプトとは「誰に、どんな価値を届けるチャンネルなのか」を一言で表す指針のことです。
例えば「就活生に業界研究を提供するチャンネル」「住宅購入検討者に安心感を与えるチャンネル」といった明確な方針があると、発信するテーマや演出に一貫性が出ます。
結果として視聴者は「このチャンネルは自分に役立つ」と認識しやすくなり、継続的に視聴してくれるようになります。
コンセプト設計を疎かにすると動画が散発的になり、ブランディング効果も半減してしまうため、最初に必ず時間をかけるべき工程です。
さらに重要なのが、自社の強みを掛け合わせる設計です。
専門知識や実績、独自データ、語り口・世界観などを核に据えると、発信テーマや演出に一貫性が生まれ、他社との差別化が進みます。
結果として視聴者は「このチャンネルは自分に役立つ」と認識しやすくなり、継続視聴につながります。
コンテンツ企画・投稿スケジュールを立てる
チャンネルの方向性が固まったら、具体的にどんなコンテンツを作るかを企画し、投稿スケジュールを立てます。テーマは複数用意しておき、一定期間ストックしておくことで運営が途切れにくくなります。
例えば1か月先までの企画をカレンダーに落とし込み、「週1本投稿」を目標に進めれば安定した更新が可能です。
さらに、トレンドに乗る企画と、ロングテールで検索され続ける企画をバランスよく組み合わせることで、短期と長期の双方で再生数を伸ばすことができます。
視聴者が「次回も楽しみ」と思えるペースを維持することが、チャンネル成長には欠かせません。
動画制作の体制を整える(内製か外注か)
動画制作は企画・撮影・編集・分析といった複数の工程で成り立っているため、どこまでを社内で対応し、どこからを外部に依頼するかを決める必要があります。
例えば、撮影は自社で行い、編集だけを外注すればコストを抑えながら品質を担保できます。
一方で、完全に外注すれば工数削減にはつながりますが、ノウハウが社内に残りにくいデメリットもあります。
重要なのは、目的とリソースに合わせてバランスを取ることです。
小規模なチームであればスマートフォン撮影から始め、徐々にプロの機材や編集者を導入する流れが現実的でしょう。
配信後のデータ分析と改善を継続する
動画を投稿した後は、再生回数や視聴維持率、クリック率(CTR)、コンバージョンといったデータを必ず確認し、改善に生かしていきます。
分析を行うことで「どの企画が伸びているのか」「どの部分で視聴者が離脱しているのか」が明確になり、次の動画作成に反映できます。
例えば、視聴維持率が低い場合は冒頭30秒の構成を改善する、CTRが低い場合はサムネイルやタイトルを見直すといった具合です。
YouTubeは投稿して終わりではなく、データを基にした改善を繰り返すことが、成果を出す上での絶対条件です。
ここまで読み進めるなかで自社で取り組むには難しいと感じるが、
「YouTube運用を外部に依頼しようと思ってもどこがいいのかわからない・・・。」
このように思うことはありませんか?
そんな方は、ぜひ以下の関連記事を参考にしてみてください。
成果を出すための運営ポイント |

前章で紹介した導入ステップを踏んだ後は、実際の運営で成果を出すための工夫が必要になります。
ここでは特に重要な4つのポイントがあります。
視聴者ニーズに合ったコンテンツ企画
クリック率を高めるサムネイルやタイトル設計
継続的な投稿とアルゴリズム理解
自社サイトや他SNSとの連携による効果最大化
これらを意識することで、ただ動画を配信するだけの状態から、成果につながるYouTube運営へと進化させることができます。
視聴者ニーズに合ったコンテンツ企画
成果を上げる企業は例外なく、視聴者が求める情報を起点にコンテンツを設計しています。
どれだけ企業が伝えたい情報があっても、視聴者の関心とずれていれば再生されません。
例えば、住宅業界なら「失敗しない家づくりのコツ」、採用なら「未経験でも活躍できる仕事紹介」といった、ユーザーが抱える疑問や不安を解決するテーマが効果的です。視聴者目線を意識した企画が、最終的に問い合わせや商談につながります。
クリック率を高めるサムネイル・タイトル設計
動画の内容が優れていても、クリックされなければ成果にはつながりません。
そのため、サムネイルとタイトルの工夫は必須です。
例えば、シンプルに「〇〇の方法」と説明するのではなく、「初心者でもできる」「3つの失敗事例」などと具体性や緊急性を盛り込むと効果が高まります。実際、多くの成功事例ではデータを見ながらデザインや文言を調整し続けています。最初のクリックを取れるかどうかが、再生数の伸びを大きく左右するのです。
継続的な投稿とアルゴリズム理解
YouTubeは継続的な投稿を評価する仕組みを持っており、一定の頻度で動画を公開することでおすすめ表示や検索結果に露出しやすくなります。
例えば、週1回でも安定して投稿するチャンネルは、短期間で大量投稿するチャンネルよりも長期的に成長しやすい傾向があります。
また、視聴者の視聴維持率やクリック率といったデータはアルゴリズムに直結するため、指標を理解して改善を重ねることが重要です。アルゴリズムに沿った運営こそが、効率的に成果を上げる近道になります。
自社サイトや他SNSとの連携で効果を最大化
YouTube単体で成果を出すのは難しく、他のチャネルと連携することで初めて効果が最大化されます。
例えば、動画概要欄に自社サイトへのリンクを設置したり、InstagramやXで動画の告知を行えば、視聴者が複数の接点を持つことで行動に移りやすくなります。
さらに、広告配信と組み合わせることで動画を短期間で多くのターゲットに届けることも可能です。
YouTubeはマーケティング全体の一部として設計することが、最終的な成果につながるのです。
企業YouTubeでよくある失敗例と回避策 |

前章では成果を出すための運営ポイントを整理しましたが、実際には思うように成果が出ずに失敗してしまう企業も少なくありません。
よくある失敗には大きく4つのパターンがあります。
再生数ばかりを追い求めて成果につながらない
動画ネタが尽きて更新が止まる
炎上やネガティブコメントへの対応不足
データ分析を行わず改善できない
これらの失敗はどの企業にも起こり得るものですが、事前に注意点を理解しておくことで十分に回避可能です。ここからは、それぞれの失敗例と防ぐためのポイントを解説します。
再生数ばかりを追い求めて成果につながらない
企業YouTubeで多い失敗が「再生数=成功」と誤解してしまうことです。
たしかに再生数は分かりやすい指標ですが、問い合わせや商談につながらなければ意味がありません。
例えば、バズを狙ったエンタメ要素の強い動画は再生されても、見込み顧客には届かないケースが多いのです。重要なのは、ターゲット層に価値を届ける設計です。再生数よりも「コンバージョンに至る視聴者が増えているか」を基準に運営方針を見直すことが必要です。
動画ネタが尽きて更新が止まる
最初は順調に投稿していても、途中で企画が尽きて更新が止まるケースも目立ちます。
原因は、運営開始時に十分なコンテンツストックを用意していないことや、ネタ出しを属人的にしてしまうことです。
回避策としては、ターゲットの検索ニーズを常に調査すること、社内の営業や顧客対応からよくある質問を吸い上げることが効果的です。
実際に「FAQ動画」「事例紹介」「業界ニュース解説」など、汎用性の高いテーマを定期的に組み込むことで、ネタ切れを防ぎ継続的に運営できます。
炎上やネガティブコメントへの対応不足
動画発信はメリットが大きい一方で、炎上リスクも抱えています。
炎上やネガティブコメントに適切に対応できないと、ブランドイメージを損なう危険性があります。
例えば、クレームコメントを放置してしまうと「対応しない企業」という印象を与えかねません。事前に社内で対応方針を決め、迅速かつ冷静に返答する体制を整えることが重要です。
また、使用する素材の著作権確認や、過激な表現を避けるといった基本的なチェックも欠かせません。
信頼を守るためには「炎上を未然に防ぐ仕組み」と「起きた際の対応フロー」の両方が必要です。
データ分析を行わず改善できない
YouTubeはデータ分析を前提に改善を重ねることで成果を伸ばしていく媒体です。
しかし、視聴回数や登録者数だけを眺めて満足し、深い分析を行わない企業も少なくありません。
例えば、視聴維持率を確認すれば「どのタイミングで離脱が多いか」が分かりますし、クリック率を見ればサムネイルやタイトルの改善点が明確になります。
これらを無視して動画を作り続けても成長は頭打ちになります。
常にデータに基づき改善サイクルを回すことこそが、成果を継続的に高める唯一の方法です。
自社でもYouTubeを活用した方が良さそうだと感じつつ、
「YouTube運用を外部に依頼しようと思ってもどこがいいのかわからない。」
このように思うことはありませんか?
そんな方は、ぜひ以下の関連記事を参考にしてみてください。
YouTube活用にかかるコストと運営体制 |

これまでに成果を出すための工夫や失敗を防ぐ方法を解説しましたが、実際に運営を始める際には「どのくらいのコストが必要か」「どのように体制を整えるか」という点も重要です。
YouTube活用の現場では主に以下の3つが課題になります。
動画制作の費用相場と外注の選択肢
自社で制作体制を整える際のポイント
代行会社やコンサルを活用するメリット
これらを理解しておくことで、自社のリソース状況に合わせた最適な運営スタイルを選ぶことができます。
動画制作の費用相場と外注の選択肢
動画制作には企画、撮影、編集など複数の工程があり、それぞれにコストが発生します。
例えば、社内で撮影したシンプルな動画なら数万円程度で済むこともありますが、外注で本格的に制作すると1本あたり数十万円かかるケースも珍しくありません。
企業が外注を利用する最大の利点は、クオリティの安定と短納期です。
ただし、費用がかさみやすいため、目的と予算のバランスを見極めて発注範囲を決めることが必要です。
自社で制作体制を整える際のポイント
コストを抑えたい場合や、自社にノウハウを蓄積したい場合は、内製化も選択肢になります。
スマートフォンや簡易的な編集ソフトでも一定のクオリティを実現できるため、小規模な企業はまず小さく始めるのがおすすめです。
ただし、企画から撮影・編集までを一人に任せると負担が大きく、継続性が損なわれやすいという課題もあります。複数人で役割分担を行う、あるいは部分的に外部を活用するなど、無理のない体制づくりが成功のカギとなります。
代行会社やコンサルを活用するメリット
外部の代行会社やコンサルを活用することで、戦略設計から運営、改善までを一貫して支援してもらえるのも有効な手段です。
特に「何から始めればよいか分からない」「リソースが不足している」という企業にとっては、経験豊富な専門家のサポートは大きな安心材料になります。
また、自社では気づきにくい改善点を提案してもらえるため、短期間で成果を出したい場合には有効です。
費用はかかりますが、時間を買う投資と考えれば十分に価値のある選択肢といえます。
まとめ|企業がYouTubeを活用する第一歩 |

企業がYouTubeを活用することで、新規顧客獲得、ブランド認知度向上、採用活動の強化など多くのメリットが得られる一方で、制作コストや継続運営の難しさ、炎上リスクといった課題も存在します。
成功事例に共通しているのは、目的やターゲットを明確にし、コンセプトを設計したうえで継続的に改善を行っている点です。
まずは小さく始め、データを分析しながら改善を重ねることが成果につながる近道です。
YouTubeは短期的な効果を狙うものではなく、中長期で資産化できる媒体であることを理解したうえで取り組むことが大切です。
もし自社だけで進めるのが難しい場合は、外部の専門家や代行会社を活用するのも有効な選択肢です。
今こそ、自社のマーケティングや採用における次の一手としてYouTube活用を始めてみてください。
また、貴社の目標を最短で達成するために必要な戦略については株式会社ビーステップへご相談ください。
ビーステップは、SNSマーケティングにおいて効果的な戦略を熟知しており、貴社の商材や目的に合わせた収益向上に直結するYouTube施策をご提案いたします。
ご支援内容は、ご提案にご納得いただいた上で実施されるため、安心して依頼いただけます。
さらに、ご支援範囲も設計から運用までワンストップで対応可能なので、業務が忙しくて手が回らない方でも、安心してご利用いただける点も魅力です。
貴社に最適な施策をご提案いたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。




















